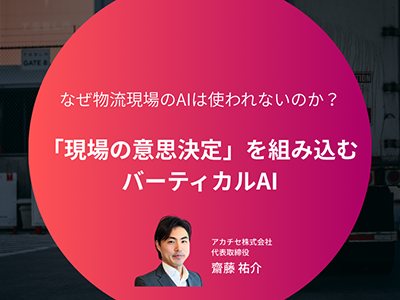教員がAIを欺いて学生の“ズル”を回避? 進化する「AI騙し」に対抗できる組織のセキュリティ強化術
【file.05】プロンプトインジェクション:自組織が惑わされないための2つの対策
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- AI事件簿 ~思わぬトラップとその対策~連載記事一覧
-
- 教員がAIを欺いて学生の“ズル”を回避? 進化する「AI騙し」に対抗できる組織のセキュリテ...
- 米企業のカスタムAIが機密データを“丸ごと提供”し大事に……AI特有の情報漏えいに正しく対...
- 「答えられません」を正しく言えるAIの作り方:プログラミングの質問に答える政策AIボットは...
- この記事の著者
-

平田 泰一(ヒラタ ヤスカズ)
Robust Intelligence Country Manager, Cisco Business Development Managerを務める。Accenture, Deloitte, Akamai, VMware, DataRobotなどを経て、デジタル戦略・組織構築・ガバナンス策定・セキ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア