※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

最新記事
産業用AIを「経営の武器」にするリーダーの条件──5%の成功企業とPoC止まりの分水嶺
深刻な労働力不足、老朽化するインフラ、そして不安定なサプライチェーン……。世界が直面するこれらの物理的な課題に対し、従来の“デスクワークのためのAI”で解決することは難しいだろう。そこで今、産業界で求められているのは、過酷な現場のコンテキストを理解し、ミッションクリティカルな局面で99.999%の精度を叩き出す「産業用AI」の実装である。インフラの再構築やデータセンター構築に向けて17兆ドル規模の資本投入が見込まれるこの「インテリジェンス時代」において、AIを単なる効率化の道具にとどめるのか、それとも物理世界のオペレーションを根底から変える武器にするのか──。2025年11月13日、米国・ニューヨークにて開催された「IFS AI Industrial X Unleashed」の議論から、成功率わずか5%という高い壁を越え、AIとともに産業の未来を創るリーダーの条件を解き明かす。
記事

PwCの「Tax AI」の現実解──複雑化する税務・経理業務にAIはどこまで活用できるか?
税務人材の確保に苦しむ日本企業は少なくない。グローバル企業では数十人規模の税務部門を抱えるケースも珍しくないが、日本の上場企業でそこまでの体制を持つ企業は限られる。人材不足に加え、Pillar 2やESGタックスレポーティングなど、税制の複雑化も進む一方だ。 こうした課題に対し、PwC Japanは2026年1月、AIを活用した業務変革の組織体制としての「PwC TS Japan」「AI Factory」の発足や、税務・経理領域におけるAI活用戦略について発表した。

なぜ物流現場のAIは使われないのか? 成果をわける「現場の意思決定」を組み込むバーティカルAI
近年、生成AIやAIエージェントの導入は急速に進んでいます。しかし、業界固有の知見が必要な現場では「PoC」止まりで本番運用に至らないケースも少なくありません。こうした中、注目されているのが業界固有の文脈を前提に設計される「バーティカルAI(Vertical AI)」です。本稿では、アナログ産業のAX(AIトランスフォーメーション)を推進する筆者が、物流現場においてなぜバーティカルAIが成果につながるのか、その考え方と実装のポイントを解説します。

150人のIT人材をどう動かす?三井不動産が「AIエージェント」と「交換留学」で狙う組織の化学反応
三井不動産は、150人超が所属するDX本部を擁し、グループ会社を含めたDXを推進中だ。2025年4月には生成AIやデータ活用をリードする「DX四部」を新設。DX本部長の分身AIエージェントを業務に活用するなど、先進的な取り組みを加速させている。そのDX本部長 宇都宮幹子さんは「2030年にはDX本部長がいらない組織にしたい」と話す。自走する組織への道筋と、その哲学を聞いた。

SNSに溢れるAIコンテンツは「愛」か「盗用」か 個と社会に問われる倫理観、解決への道筋は
生成AIの急速な普及は「AIの民主化」をもたらした一方、生成物における著作権侵害やコンテンツの価値毀損といった課題も浮き彫りになってきた。クリエイターの権利、コンテンツの真正性を担保し、健全な「AIコンテンツ」を享受するための道筋はあるのか。

三井化学とIndeedが壊した「AI活用の壁」──“20年来のアドオン地獄”と“2年待ち”を打破
生成AIの登場により、企業のDXは「導入」から「実利の創出」という新たなフェーズへ突入した。しかし、AIを活用しようとしても、社内に散らばるデータの分断や組織文化、レガシーシステムが壁となり、変革が思うように進まないケースが後を絶たない。Salesforceが開催した「Agentforce World Tour Tokyo」では、「CDO・CIO・経営企画・人事と考える、データ×AI×人材──組織を変革する次世代の成長戦略」と題したパネルディスカッションを実施。三井化学 常務執行役員 CDOの三瓶雅夫氏、Indeed CIO 兼 CSOのアンソニー・モイサント氏が登壇し、モデレーターをSalesforce EVP Chief Digital Officerのジョセフ・インゼリロ氏が務めた。AIが真に成果を生むために必要な変革の全体像を、三井化学とIndeed、両社の実践から探る。

味の素と東京海上が示す、Snowflake/Databricksを活かした“AIレディな基盤構築術”
生成AIの台頭により、企業のデータ活用はさらに高度化し、単なる分析を超えた次のフェーズへと移行しつつある。しかし、その足元にあるデータプラットフォームの整備において、サイロ化したシステムや形骸化した運用に頭を抱えるIT部門は少なくないだろう。2025年11月7日に開催された「Data Tech 2025」では、製造業と金融業という異なるフィールドで大規模なデータ基盤構築をけん引する2名のリーダーが登壇。モデレーターの谷川耕一氏(EnterpriseZineチーフキュレーター)の進行のもと、味の素の小林文宏氏と東京海上日動システムズの木村英智氏が、全社規模のデータプラットフォーム選定から現場への定着に向けた対策まで、その実践知を語り合った。
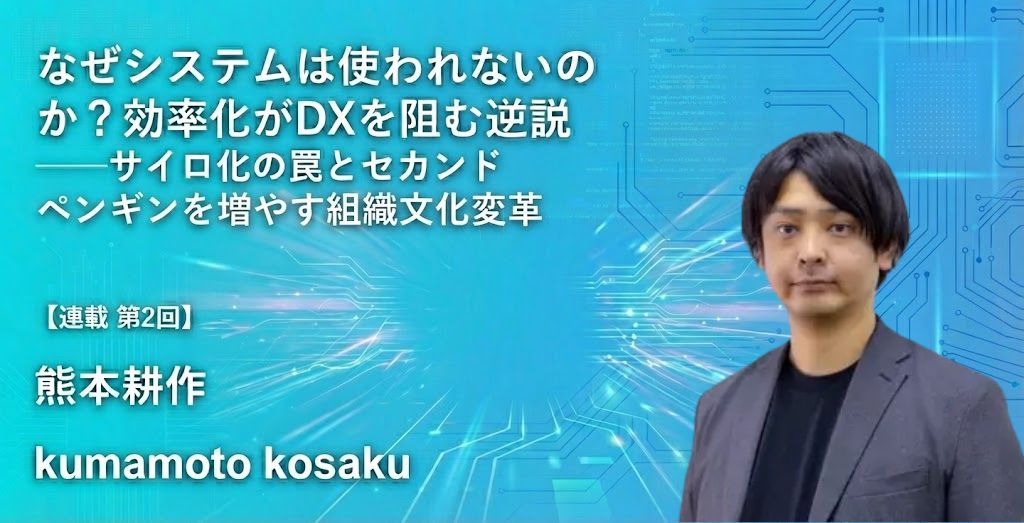
なぜシステムは使われないのか?効率化がDXを阻む逆説──サイロ化の罠とセカンドペンギンを増やす組織文化変革
「システムを導入したのに、誰も使わない」──この悩み、あなたの組織にもありませんか。実は、DXがうまくいかない原因の多くは技術ではなく、組織文化にあります。効率化を追求するほど部門間の壁が高くなり、データ共有が進まない。この矛盾を解く鍵は、最初に挑戦するファーストペンギンを支援し、それに続くセカンドペンギンを増やすことです。心理的安全性、ナレッジシェア、部門を越えた連携──小さな成功体験の積み重ねが、組織を変えていきます。

今のERP、10年後も使えるか?進化系iPaaSが支える“コンポーザブル”なシステムへの変革ビジョン
2025年11月18日、アイ・ティ・アール(ITR)が主催するカンファレンス「IT Trend 2025」が開催された。シニア・アナリストを務める水野慎也氏が登壇した講演では、「10年後を見据えたIT部門の構造改革ビジョン」と題し、AIが前提となる未来に向けたアーキテクチャー設計と、IT部門が進むべき新たな道筋が提言された。

ゆずたそ氏が予測、AI時代のデータ基盤はメッシュ構造/今後はデータの「中間テーブル管理方法」が肝に
生成AIが急速に普及する一方で、組織の現場で「期待を超える成果」にはまだ届いていないのが実情だ。その成否を分ける大きな要素は、データの質と量である。だが現場に目を向けると、データのサイロ化やメタデータの不整備といった課題が足かせとなっている状況が散見される。生成AIの登場でデータ活用の現場が大きく変化する中、データ基盤の現在地点と主要論点について、“ゆずたそ”こと風音屋 代表取締役 横山翔氏がEnterpriseZine編集部の主催イベント「Data Tech 2025」で考察した。

AIで好調のOracleは「第4のハイパースケーラー」となれるか? 2026年の行方を占う
2025年、生成AIの進化はモデルの精度競争から、それをいかに実際のビジネスへ組み込むかという「エージェント活用」のフェーズへと移り変わった。この激動の1年において、GoogleやMicrosoft、Amazon Web Services(AWS)といった既存のメガクラウドベンダーと並び、あるいはそれ以上の熱量で市場の注目を集めたのがOracleだろう。Oracleは、OpenAIとの大規模なAIインフラに関わる協業を皮切りに、GeminiやLlamaといった複数モデルをOCI(Oracle Cloud Infrastructure)上で提供することで、「第4のハイパースケーラー」としての地位を確立した。さらにERPやHCMといった広範なSaaSアプリケーション群にAI機能を深く統合し、データベースそのものをAIに対応させるための戦略を加速させている。同社が目指すのは「企業データと生成AIの極限までの接近」だ。

AI時代のデータ分析、最後に問われるのは「人間力」 DMMの実践知に見るデータ専門職の新たな存在意義
DMM.com(以下、DMM)はインターネット黎明期にビデオ通販・動画配信サイトから事業を開始し、今では電子書籍、ゲーム、英会話、金融、通販など数多くの事業を展開する企業へと成長している。その特徴は「DMM.com」を通じて多彩なデジタルコンテンツを提供している点にある。早い段階からユーザーの利用履歴や嗜好データに基づいたレコメンドやUI/UX改善に取り組んでおり、「データドリブン」が企業文化として根付いているようだ。DMMにおけるデータ分析の取り組みについてリーダー2名に訊いた。

来る「AI産業革命」に備える関西電力、“脱JTC宣言”でAIレディな企業への変身を急ぐ
生成AIの登場により、企業は「AI活用」のフェーズから「AI前提の事業再構築」へとパラダイムシフトを迫られている。2025年11月、EnterpriseZine編集部主催の「Data Tech 2025」のクロージングセッションに、関西電力 理事 IT戦略室長の上田晃穂氏が登壇。上田氏は、2030年に到来すると予測される「AI産業革命」を見据え、同社がいかにして伝統的な日本企業(JTC)の体質を脱し、「AIファースト企業」へと変貌を遂げようとしているのか、そのビジョンと実践の裏側を語った。本稿では、同社のDX戦略の中核を成す「データマネジメント」「人材育成」「組織風土改革」の三位一体の取り組みをレポートする。

【特集】ITベンダー&コンサル企業6社に聞く、2026年の展望 企業のIT変革を支えて見えた市場変化
「2025年の崖」の到来、AIエージェントの台頭、大企業に相次いだランサムウェア攻撃被害など、多様なトピックがIT業界を騒がせた2025年。DX推進やセキュリティの強化など、多くの命題に追われる企業が数多ある中、そのIT変革を間近で支えるITベンダーとコンサルティングファームは、この激動の一年をどう見ているのでしょうか。年末特別企画として、第一線を走り続ける6社に今年の総括・来年の抱負をうかがいました。

【特集】PKSHA・セールスフォース代表/ソニー・ダイハツAI推進リーダーに聞く2026年の抱負と予測
生成AIが台頭したかと思えば、今や人とエージェントが協働する「AIエージェント時代」が到来しつつある今日。2025年も、AIは驚くべきスピードで進化を続けました。ITベンダーから次々と新たなAIプロダクトや構想が発表されているほか、世界中で新興AIカンパニーも次々と登場しています。そして、日本企業でのAI利活用においても様々な事例が出てきており、これらが将来の競争力や成長力を左右することになるでしょう。そこで、年末特別企画として、AIカンパニーからはPKSHA Technologyとセールスフォース・ジャパンに、そしてユーザー側からはソニーグループとダイハツ工業に、2025年の振り返りと2026の抱負についてインタビューを実施しました。2026年のAI進化と活用は、どのような方向に向かうのでしょうか。

【特集】財務・会計のキーパーソン5人に聞く──経済・テック・監査・実務のプロが2026年を見通す
「開示の質」が問われたサステナビリティ報告、「実務への実装」が試された生成AI、そして、「不確実性」を前提とした経営戦略の策定・実行……2025年は、待ったなしの課題に財務・会計部門が真正面から向き合った一年でした。従来の価値基準や業務プロセスが根底から見直される中、多くのリーダーが変革のプレッシャーと手応えを同時に感じたことでしょう。また、EnterpriseZine編集部では『財務・会計Online』を立ち上げました。そこで今年は、各社の第一線で奮闘する有識者やCFOなどのリーダーたちにメールインタビューを実施。激動の2025年をいかに乗り越え、2026年をどのような戦略で迎えるのか。その総括と展望をお届けします。

AIエージェントの現況・課題はSaaSブームの頃に似ている──企業が構築すべき次世代のIT環境とは?
あるアプリケーションのデータを、別のアプリケーションでも使いたい。アプリケーション統合やデータ統合のニーズは、オンプレミス時代から続く普遍的なものだ。しかし、テクノロジーの進化にともないその実現手段も変化している。そして、AIエージェントがソフトウェアのアーキテクチャを大きく変えようとする今、企業はどんな環境を整えるべきか。API連携のリーダーであるMuleSoftの幹部に尋ねた。

時価総額5兆ドルを一時突破したNVIDIA、強さの秘密は?──フアンCEOの鑑定眼とリーダーシップ
NVIDIAの時価総額が一時的にではあるが5兆ドルを突破したことが大きな話題になった。時価総額ランキングで上位にいる他のIT企業(Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft)の多くがプラットフォーマーと呼ばれる総合的なITサービス事業者であるのに対して、NVIDIAは唯一の半導体メーカーだ。なぜ、NVIDIAはそうした株式市場から期待されるような銘柄に成長したのだろうか? その背景には、NVIDIAの成長戦略と創業以来32年以上一度も変わっていないジェンスン・フアンCEOの技術を見る「鑑定眼」、そしてフアン氏を頂点としたフラットな組織体制が大きな原動力になっている。

三菱UFJトラストシステムは3ヵ月で「開発支援AI」を内製化 未経験の若手エンジニアが奮闘
三菱UFJ信託銀行と日本マスタートラスト信託銀行を中心としたシステム開発を担う三菱UFJトラストシステムは、開発力強化を目指して「生成AI」を活用した開発支援エージェント「AIDE(エイド)」を自社開発した。AWS(Amazon Web Services)の「Generative AI Use Cases JP(GenU)」を活用し、若手エンジニア主導でわずか3ヵ月という短期間でのリリースを実現している。その背景にある危機感、そしてMVP(Minimum Viable Product)開発を通した人材育成の挑戦とは。

AI活用の成否は「データ品質」で決まる 成果を生むためのインフラ戦略
2025年11月7日にEnterpriseZine編集部が開催したオンラインイベント「Data Tech 2025」において、デル・テクノロジーズは「進化を続ける『Dell AI データプラットフォーム』が実現する世界」と題して講演を行った。同社のアドバイザリシステムエンジニアである安井謙治氏と、執行役員統括本部長の森山輝彦氏が「Dell AI Data Platform」の全体像、そしてAI時代における“データ民主化”戦略の鍵となるコンセプトについて詳細に解説した様子をレポートする。

エージェンティックAIは銀行業務変革にどう貢献するか? nCinoが発表した5つのエージェント
人口減少、ゼロ金利、レガシーシステム――難題が山積する日本の金融機関に対し、nCino(エヌシーノ)のCEOショーン・デズモンド氏は「現状維持こそが進歩の敵」と訴えた。11月19日の「nCino Summit Japan 2025」で発表されたのは、銀行業務を変革する5つのAIエージェント「Digital Partners」。経営幹部から顧客対応まで、役割別に設計されたエージェンティックAIが、業務効率化と収益機会の発見を実現する。2,700超の金融機関から蓄積した独自データを武器に、nCinoが描く銀行変革の未来図を紐解く。

OpenAIの最高戦略責任者と語る、日本が「世界で最も信頼されるAIインフラ国家」になるための条件
2025年12月9日、OpenAI Japanは都内で「AIインフラ」をテーマとしたトークセッションを開催した。OpenAI本社から最高戦略責任者(Chief Strategy Officer)のジェイソン・クォン氏が来日し、AIインフラ構築で繁栄を築くために国家・産業が乗り越えるべき課題と、日本がAIインフラ構築に持つポテンシャルについて語った。また、金融機関の立場から官民のAIインフラ構築を支える三菱UFJ銀行、さらにはAIインフラに欠かせない部品の製造を手掛ける村田製作所も登壇し、それぞれの立場から見えているAIインフラ構築の制約と、その解決のアプローチについて意見を交わした。

SAPの構造化データ専用モデル「SAP-RPT-1」登場 LLMが解けないビジネス課題を解決できるか
SAPは、2025年11月4日から6日にかけて開発者向けの年次イベント「SAP TechEd 2025」を開催した。この記事では基調講演の数多くの発表の中から、4つのハイライトを紹介する。

新たに実用化が迫る「量子AI」は何がすごいのか、AIの進化を前に必要な心構えは?
2025年7月24日に、「SAS Innovate On Tour Tokyo」が開催された。5月に開催されたSAS Innovate(米オーランド開催)での発表内容やメッセージを、日本市場向けに届ける場だ。ちなみにSAS Institute(以下、SAS)は、2026年に創業50周年を迎える。間違いなく“最古のアナリティクスベンダー”の一社といえるが、今年のInnovateでは「量子AI」など、関心を呼ぶ新たなキーワードも出てきた。東京でのイベント開催に際し、同社で技術責任者を務める一人であるディーパック・ラマナタン(Deepak Ramanathan)氏にインタビューを行う機会があったため、5月のオーランドで見聞きした内容も踏まえ、気になったことを訊いてきた。

システムと組織の在り方を再定義する時──Workdayの最高責任者たちに訊く「次世代ERP」の真価
大手ERPベンダーのWorkday(ワークデイ)が、AIによる企業変革の新たな段階を予感させる数々の発表を行った。本稿では、同社が2025年9月に米サンフランシスコで開催した「Workday Rising 2025(以下、Rising)」の期間中に行われた、APAC Japan地域の報道陣とのグループインタビューの内容をお届けする。インタビューに応えたのは、同社の営業やマーケティングなどを統括するロブ・エンスリン氏と、製品・技術全体を統括するゲリット・カズマイヤー氏だ。ビジネスとテクノロジーの両面から、人事・財務領域を中心にオープンプラットフォームを提供する同社がAI時代に重んじる思想と戦略、さらには今回のRisingで掲げられたERPの再定義を意味する「Next-Generation ERP(次世代ERP)」の意図などを解説いただいた。
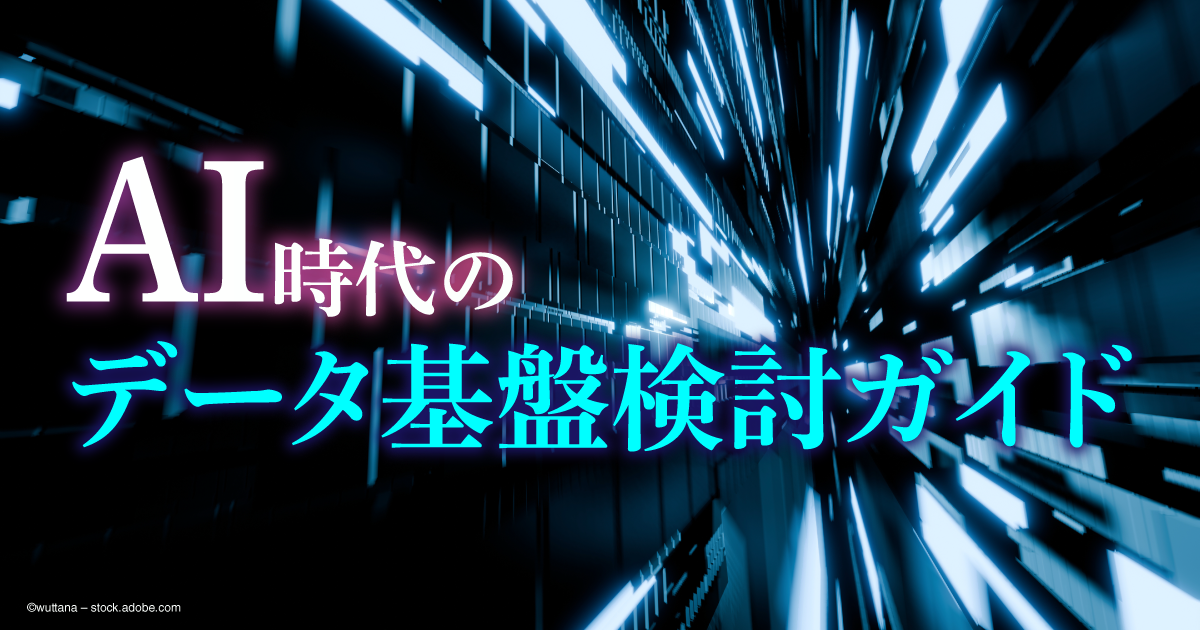
AI活用が本格化するのに、“土台”は今のままか?「AI前提」で考えるデータ基盤の在り方と実装ステップ
生成AIがビジネス変革のツールとして急速に普及する中、その成否を握るカギとして「データ基盤」の在り方が改めて問われている。多くの企業でAIによるビジネスの変革が進む、いわゆる「AI時代」において、従来のデータ基盤が抱える課題を乗り越え、AI技術の可能性を最大限に引き出す次世代アーキテクチャとはどのようなものか。本稿では、データ基盤の構築・整備・運用を担当する方に向け、AI活用を前提としたデータ基盤が直面する具体的な課題を整理し、必要な要件、そして実現に向けた検討ポイントを深掘りした。また、組織がAI時代を生き抜くためのデータ戦略と、データ基盤担当者に求められる新たなスキルセットについても解説する。

“レジェンドCIO”5人衆と旅先で考える「これからの情シス」──2030年までに解決しておきたい課題
沖縄に5人のITリーダーが降り立った。激動のAI時代にあって走り続けることは大事だが、少し立ち止まって本音で語り合うことも、リーダーにとって必要な時間であろう。テーマは「日本企業の課題とCIOの役割」。2030年までに残したくない技術負債は。6時間に及んだ議論の一部始終を紹介する。

変革を遠ざける「DXじゃない論争」 ──「真のDX」論争が奪った5年と、AIが拓く新たな実装軸
「それはDXではない」という定義論争が、現場の変革を5年も停滞させた。小さな改善を否定する「真のDX」論から脱却し、AI時代の今こそ、現場の実行力に基づく「実装型DX」へ舵を切る時だ。連鎖する小さな成功こそが組織を変える鍵となる。

選挙への介入だけではない「誤情報/偽情報」問題 4つの対策、ガートナーのアナリストが提言
世界経済フォーラムが発表した『Global Risk Report 2025』によれば、向こう2年の短期では「誤情報と偽情報」が首位のリスク項目になった。このリスクに対して、企業経営者はどうアプローチするべきか。来日したガートナーのアナリストに聞いた。

ビジネスメタデータ整備は「大きな戦略、小さな実行」で “AIレディ”な環境実現に向けた具体的ポイント
EnterpriseZine編集部は、2025年11月7日にオンラインイベント「Data Tech 2025」を開催。Quollio Technologies 阿部恵史氏の講演「プロンプトでは届かない──AIが"意味"を理解するための『ビジネスメタデータ』戦略」では、AI活用で期待以上の成果を出すために不可欠な要素が解説された。阿部氏は、生成AIの活用に取り組む日本企業のうち、期待以上の効果を得ているのはわずか10%に過ぎない現状を指摘。この課題を乗り越え、AIがデータの背景や文脈を理解するには、人の暗黙知である業務コンテキストを形式知化し「ビジネスメタデータ」として整備することが不可欠だと強調した。

「決断力の変革」こそがデータ活用の真価──カギとなる“産業”を知り尽くした自律型デジタルワーカーとは
データ活用の真の価値は、効率化ではなく「決断力」を変革することにある。多くの企業がAIの導入段階で苦戦する中、IFSが提供するのは、現場・マネージャー・経営陣の“意思決定”を支援する産業特化型のAIアプローチだ。2025年11月7日の「Data Tech 2025」に登壇したIFSジャパンの竹中康高氏は、すでに200社以上のユースケース・年間約2.5億の作業件数という同社のAIの実績を背景に、コニカミノルタビジネスソリューションズ(英国)が実現したROI 4.36倍の達成事例などを紹介。さらに、自律型AIのデジタルワーカーが、顧客からの1本のメールを起点に自動的に判断・行動し、人間は承認を下すだけで最後のアクションまで完結するサプライヤー連携システムのデモも行われた。

【中外製薬×ふくおかFG】AI時代のDX推進「実行・投資・文化醸成」の壁に、両社はどう立ち向かった?
DX推進において、アイデア創出から実行、スケール、そして組織変革まで、企業は必ず複数の「壁」に直面する。2025年10月21日に行われたエクサウィザーズ主催イベント「AI Innovators Forum 2025」では、中外製薬とふくおかフィナンシャルグループのDX推進リーダーが対談した。ともにデジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)企業である両社は、どのように壁を打破したのか。その実践的な方法論を語り合った。

生成AI時代に“技術特化人材”は不要? 事業とITをつなぐ「CoE型人材」を育成する3のメソッド
多くの日本企業、特に規模の大きな日本の伝統的企業「JTC(Japanese Traditional Company)」では、デジタルや生成AIの活用に関する議論が進む一方で、実際の変革が思うように進んでいないケースが少なくありません。その原因の多くは技術そのものではなく、マインドセット、組織体制、開発プロセス、人材といった「非技術的な構造」にあります。つまり、変革を支える“人と組織の仕組み”が整っていないのです。そこで、連載「住友生命 岸和良の“JTC型DX”指南書」では、筆者が住友生命保険での実務経験をもとに、JTCの変革に必要な視点を解説しています。第9回となる今回は、生成AI時代に求められる「CoE型人材(センターオブエクセレンス人材)」の育成をテーマに、その実践の方向性を考えます。

AIが出した答えを、投資家に説明できますか? SAS中村氏が語るAI時代の意志決定リテラシー
データは増え続け、コストも膨らむ一方で、企業の収益性向上は追いついていない。統計分析システムの老舗SAS Institute Japanのコンサルティング事業本部長・中村洋介氏が、「データ横丁」の対談企画で明かしたのは、データ活用の本質を見失いがちな企業の現実だった。意思決定に必要なデータとは何か。データサイエンティストは今後どう変わるべきか。AI時代に問われる「判断の説明責任」について、率直に語り合った。

日本企業の「人への優しさ」がAI活用の足かせに?経済産業省が官民連携で進める“現場データのAI化”
STT GDC Japanは2025年11月11日、イベント「Practical Insights」を開催。本記事では、イベントに登壇した経済産業省 渡辺琢也氏の講演「経済産業省のAI政策の動向と展望」で語られた日本企業のAI活用における現状課題やそこに対する経済産業省のアプローチなどを紹介する。人口減少や少子高齢化、デジタル赤字といった課題が山積みな“課題先進国”である日本で、AI活用はそれらの課題を打破するカギを握っている。渡辺氏は日本企業でAI・データ活用が思うように進まない要因をどのように分析し、次の一手を示したのか。

松屋 古屋毅彦×テックタッチ 井無田仲──伝統と革新の両立を実現する、松屋銀座のデジタル変革の舞台裏
消費行動の多様化やECの台頭など、百貨店業界はかつてない変革期を迎えている。創業150年を超える老舗百貨店の松屋は、2025年5月1日に銀座店が開店100周年を迎えた。長い歴史を持つ百貨店の中でもいち早くデジタル化に取り組み、リアルとオンラインを融合した新たな顧客体験の創出を進めている。創業家の5代目として同社を率いる古屋毅彦社長は、ITの力で「リアルの価値」をどう再定義していくのか。テックタッチ代表 井無田仲氏が、百貨店DXの現場とリーダーシップの本質に迫った。

キリンはAI時代を「データメッシュ」で戦う──独自生成AIの活用拡大で新たに挑むマネジメントの現在地
キリンホールディングス(以下、キリン)は、DX推進の一環として全社共通のデータ基盤構築を進めるとともに、自社特化型の独自生成AI「BuddyAI」を開発、その活用を全社に拡大させている。このBuddyAIの本格的な活用は、全社的なデータマネジメントのあり方を変える大きな契機となっているという。BuddyAIの活用拡大にともなうデータマネジメントの課題と取り組みをテーマに、データ基盤の整備・運用の現状、データガバナンス強化の方針、そして社員の意識改革について話を訊いた。

AIを“意のまま”に セールスフォースが解決率77%の知見を注ぐ「Agentforce 360」
セールスフォース(Salesforce)が提供する自律型AIエージェントプラットフォーム「Agentforce」が2年目を迎えた。発表以来、顧客数はグローバルで12,000社超と、過去に例のないペースで成長を続けている。同社の年次イベント「Dreamforce 2025」の2日目に行われた、Agentforceに関するキーノートでは、最新バージョン「Agentforce 360」について、多くの強化ポイントが紹介された。本稿では、特に大きく取り上げられた4領域のアップデート内容を解説する。

AIエージェント時代のセキュリティに果たして正解はあるのか? 1年半以内に起こる“とある問題”とは
米国ナッシュビル(テネシー州)で2025年9月に開催された、Proofpointの年次フラッグシップイベント「Protect 2025(以下、Protect)」。そこでは、人とAIエージェントが協働する時代における組織・IT環境のセキュリティとガバナンスの在り方について、様々な角度から議論が交わされた。その中から、同社のCTOとAI・データ最高責任者が各国メディアに対し語ったセッションの内容をお届けする。両氏が示したのは、セキュリティ業界全体のパラダイムシフトを予感させるビジョンだった。

Santenと日本ハムはマイクロソフトの生成AIツール導入でどう変わった?──研究/開発での活用に脚光
日本マイクロソフトは2025年9月、大阪にて「Microsoft AI Tour Osaka」を開催した。様々な業界での生成AI活用事例が紹介された中から、本稿では参天製薬(以下、Santen)と日本ハムの取り組みに注目する。単に生成AIを導入するだけでなく、それぞれの業務特性や企業文化に合わせた活用を模索し、成果につなげている点はきっとヒントになるだろう。

調達部門の働き方を変える“次世代のAriba”、人とAIが協働する調達プロセスの在り方とは?
不確実性の高い経済・事業環境でも、「支出」は比較的コントロールの容易な要素に見える。もちろんコスト削減は大事だが、経営幹部にはそれ以上のことが求められている。SAP Connect 2025の「Spend Management Connect」では、グローバル企業で働く調達部門のリーダーを対象に、調達プロセスの自動化を進め、よりスマートなインサイトを提供する次世代Aribaの紹介があった。

金融機関が頼る“HAクラスター”の価値 AI時代の「止められないシステム」をどう守るか
システムに極めて高い可用性が求められる金融機関や特定社会基盤事業者を中心に、数多くのシステムを保護してきたHAクラスターソフトウェア「LifeKeeper」。これまで長らくオンプレミスや仮想環境で使われつづけてきた同製品だが、クラウドやAIの台頭で状況は変わったのか。金融業界を中心とした現況を皮切りとして、HAクラスターソフトウェアの過去・現在・未来について、サイオステクノロジーの吉岡大介氏とEnterpriseZine編集長 岡本が語り合った。

なぜAI活用は「続かない」のか? “あと一歩”の企業こそ、パワーユーザーを置くべき理由
AIで最も難しいのは、導入ではなく「継続的な活用」です。連載『AI活用の真髄──効果的なプロセスデザインとビジネス変革』では、業務コンサルタントの視点でAI導入を支援している小坂駿人氏(パーソルビジネスプロセスデザイン)が、AIを「真のビジネス変革」につなげるためのポイントを5回にわたって解説。最終回となる本稿では、継続的なAI活用に向けた“体制づくり”のコツを紹介した上で、進化を続ける「AIとの向き合い方」を考察します。

金融機関は紙・Excel文化から脱却できるか? 地銀や信金も「データ活用」「内製化」に注視
業務効率化やサービス向上に向けて「データ活用」に取り組む金融機関が増えてきた一方、業界特有の厳しいセキュリティやガバナンス要件を前に二の足を踏む金融機関もまだまだ多い。その中、金融機関に対して積極的にソリューションを展開しているのがウイングアーク1stだ。同社の金融ビジネスを率いる加茂正孝氏に、金融業界が抱えているニーズや課題について、EnterpriseZine編集長の岡本が聞いた。

GenAI登場で大きく変わったAI開発者の仕事、WorkdayのAIリーダーが重んじる開発の哲学とは
2025年9月に、米国サンフランシスコで年次フラッグシップイベント「Workday Rising 2025」を開催したWorkday(ワークデイ)。今年は、“Next-Generation ERP(次世代ERP)”の体現を掲げ、AIと人が自然と協働する世界を実現する様々な機能やプラットフォームの拡張、新たなエージェンティックAIの発表を行った。そんな同社でAI責任者を務めるシェーン・ルーク(Shane Luke)氏に、AI開発者として現在のテクノロジーの潮流をどう捉えているか、またWorkdayの進化の方向性や、AI開発の舞台裏について話を伺った。ユーザー側だけでなく、AI開発に携わる方にもぜひご一読いただきたい。

“止められない”システムの運用管理の現場で今求められていることは? 日立製作所「JP1」からひも解く
長年にわたり日本のエンタープライズシステムの安定稼働を支えつづけてきた、日立製作所の統合システム運用管理「JP1」。システム停止が許されない金融機関など、ミッションクリティカルシステムを抱える企業で利用されている。近年、そうした領域においても、クラウドやAIなどの先進技術を積極的に取り入れる動きは活発化する中、どのような課題を企業は抱えているのか。EnterpriseZine編集長の岡本が日立製作所 高木将一氏に話を聞いた。

AIネイティブなGRCツール選定のポイント──“業務をシステムに合わせる”ためにIT部門がすべきこと
AIの普及にともない、ITシステムのガバナンスを担保するIT部門の役割は重要性を増す一方である。このような中、リスク全般の効率的な管理に有効なのが、GRC(Governance, Risk, Compliance)を統合的に管理するGRCツールだ。連載「GRCツール導入の羅針盤 ~AI時代のITガバナンスを確立~」では、ITガバナンスに悩むIT部門担当者にGRCツールという選択肢を提示し、自社の課題に沿った選定方法、導入のポイントを解説。前回の連載記事では、ガバナンス・リスク・コンプライアンス領域(GRC領域)への期待が高まる一方で、“デジタル後れ”が発生しており、CIOやIT部門が何らかの役割を果たす必要があることについて述べた。連載第2回となる本稿では、デジタル化が遅れる原因を深掘りしつつ、IT部門が果たすべき役割に触れ、GRCツール導入において検討すべきポイントを解説する。

なぜSalesforceはSlackを全てのAIの起点にするのか ── 「エージェンティックOSとしてのSlack」戦略とは
10月14日から16日にかけて行われたDreamforce 2025。今年の基調講演でマーク・ベニオフ氏が強調していたのが「エージェンティックOSとしてのSlack」である。その後に行われたSlackの製品キーノートでは、SlackによるSalesforceの再構築という観点から、その詳細が明らかになった。

“触れない”基幹系データをAIへ レガシーを残しながらも「次世代データ連携基盤」を構築する術とは
膨大な量のデータを日々処理する金融システムは、社会インフラとして高い堅牢性や安全性が求められる。それと同時に「生成AI」の台頭を背景として、ミッションクリティカルなシステムから発生するデータを活用した業務効率化、新サービスの開発などにも期待が寄せられている状況だ。そうした中、データの安全性を担保しつつ活用を促進するためには、どのような要件が必要とされるのか。これまで「HULFT」をはじめ、数多くの金融機関にデータ連携ソリューションを提供してきたセゾンテクノロジーの福泊晶氏と、EnterpriseZine編集長 岡本が語り合った。

規制一辺倒の時代は終焉──AIガバナンス“潮目”の2025年、経営層の「法的義務」にどう備える?
AIエージェントの時代が到来し、AIは企業成長の不可欠な要素へと劇的に進化しつつある。しかし、その裏にはプライバシー侵害、セキュリティ脅威、バイアス、虚偽情報といった多様なリスクが潜んでいる。技術革新が法整備のスピードを上回る現在、企業は「正解のない状況」で最適な選択を取り続けなければならない。EnterpriseZine編集部主催イベント「Security Online Day 2025 秋の陣」に登壇したスマートガバナンス 代表取締役CEO 兼 京都大学特任教授の羽深宏樹氏は、AIガバナンス体制の構築から国際的なルール形成の最新動向まで、企業が直面する現実と具体的対策を解説した。

トライアルの西友買収でどんな“化学変化”が起こるのか?──技術革新を担うRetail AIに訊く
トライアルホールディングスは、7月1日付けで西友の全株式を取得し、完全子会社化を完了した。今後はセルフレジ機能付き「スキップカート」や顔認証決済機能付きのセルフレジといった店舗DXの強化、出店拡大、商品開発など多方面でグループシナジーを追求する。トライアルの技術革新を担うRetail AI 代表取締役 COO 永井義秀氏は、「異なる商圏と顧客を持つ両社のデータが融合することで、さらに深く広い顧客理解が可能になる」と語る。それぞれの強みを生かし、ともに描く未来像とは。

「中小だから……」は言い訳 超アナログな地方中堅企業を2年半で変貌させ、四国のITをリードする存在に
香川県に本社を構える、創業115年の老舗・船舶エンジンメーカーのマキタは、15年前まで情シス不在で“IT原野”だった。情報セキュリティベンチマークは平均を大幅に下回る状況。それを打破しようと立ち上がったのが、当時一般事務職だった高山百合子さんだ。「さっさと帰りたい」を原動力に業務効率化を始め、やがて無秩序な社内ITに気づき、上司にシステム専任担当になりたいと直談判。一度は却下されるも諦めず、ひとり情シスとして様々な改革を行った。そうした成果が評価され、今は執行役員として経営とIT戦略をけん引する立場となった高山さんに、15年の歩みを聞いた。

レガシーなデータ基盤を刷新する際、注意すべきポイントは?成功企業・有識者から「AI時代の解」を学ぶ
2025年11月7日、EnterpriseZineはオンラインイベント「Data Tech 2025」を開催する。開催が間近に迫った今、本記事ではイベントの見どころをセッションごとに紹介。自社のデータプラットフォーム構築に課題を感じている方、必見の内容だ。

「Oracle AI Database 26ai」登場 次世代AIネイティブDBとオープン化戦略
米国時間10月14日、Oracle AI World 2025において「The “AI for Data” Revolution is Here – How to Survive and Thrive」と題した基調講演が行われた。AIをデータ管理の中核に組み込んだ、次世代AIネイティブ・データベース「Oracle AI Database 26ai」の発表に加え、エンタープライズのデータとAIを安全に接続し、エージェント型アプリケーションの作成・展開を可能にするプラットフォーム「Oracle AI Data Platform」の一般提供開始が公表された。

「企業内消防隊」を救え──SAPが挑む、混乱するサプライチェーンの即応最適化
地政学リスク、関税措置、原材料不足──「消防士」のように混乱に対処し続けるサプライチェーン担当者に、SAPが新たな武器を提供する。SAP Connect 2025で発表された新製品「Supply Chain Orchestration」は、ナレッジグラフとAIを駆使し、多階層のサプライチェーン全体をリアルタイムで可視化。リスクの早期検出から代替案の提案まで、不確実性の時代に即応できる最適化基盤の構築を目指す。

データサイエンティストを疲弊させてきた“分析前処理”が「Gemini」で改善!活用法を実例で解説
第6回は「Geminiと協働するデータサイエンス業務の新しい形」と題して、データ分析業務における具体的なGeminiの活用事例を紹介します。執筆は、auコマース&ライフの奥野が担当しました。データサイエンティストとして、弊社が運用する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」の主要KPIの動向レポートやユーザー行動の分析など、事業推進に必要な統計解析を行っています。今回はそうした実務から得られた知見を共有します。

人材は「天下の回りもの」NICT園田氏が語る、生成AI時代のセキュリティ人材育成で企業が見るべき視点
XaaSの登場によりサイバー攻撃が激化している現在、それに対処するセキュリティ人材は圧倒的に不足している。日本企業で特に深刻なのは、セキュリティ戦略・企画を担う人材の不足だ。必要な人材の獲得・育成に際して考えるべきことは何か、経営層や管理職など多忙なプロパー人材にセキュリティ戦略・企画のトレーニングを施すうえでリーズナブルかつ効果的な方法はあるのか。また、昨今は「生成AI」を抜きにしてセキュリティ施策や人材育成を考えることはできない。セキュリティ業務における人と生成AIの役割分担をどう考え、人材育成に注力していくべきか──2025年9月4日〜5日に開催された「Security Online Day 2025 秋の陣」で、NICT(情報通信研究機構)ナショナルサイバートレーニングセンター長の園田道夫氏が「生成AI時代のセキュリティ人材育成のあり方」について語った。

ガイドラインだけでは安心できない──生成AI時代のセキュリティリスクに対抗できる“仕組み”とは?
生成AIの利用が当たり前となりつつある今、企業をはじめとする組織は「AIを狙ったサイバー攻撃」「AIの利用を通じた意図せぬ情報流出」「AIを悪用した攻撃」などに対応できる体制を構築しなければならない。生成AI利用のガイドラインだけでは、ユーザーのリテラシーや解釈に依存する部分があまりにも大きいからだ。2025年9月に開催された「Security Online Day 2025 秋の陣」にて、A10ネットワークスの高木真吾氏が講演を行った。何をどうすれば、「生成AI時代のリスクに対抗できる」と胸を張れるのか。その方法をお届けする。

医師の負担軽減へ──地域医療機関が“院内生成AI”による「退院時サマリ」自動作成をオンプレミスで実装
生成AIはパブリッククラウドとの連携を中心に進化を遂げてきたといっても過言ではない。その一方で、大企業やセンシティブなデータを扱う業界からはセキュリティ/プライバシーリスク、あるいはデータ主権(データソブリン)の観点から、パブリッククラウドではなくプライベートクラウドやオンプレミスの環境でAIインフラストラクチャを利用したいという「プライベートAI」に対するニーズが大きくなりつつある。既にそうしたニーズに応えるサービス提供も始まっており、たとえばBroadcomによるVMwareポートフォリオをベースにした「VMware Private AI」や、KyndrylとDell Technologiesが連携する日本企業向けのプライベートAIクラウドマネージドサービスなどが当たる。こうしたサービスは大企業での利用が前提となっているケースがほとんどだ。しかし、センシティブなデータの扱いに悩むのは大企業だけではない。特に医療機関や教育現場、地方自治体といった公共の福祉に貢献することを求められる組織においては、個人情報を含む様々なセンシティブデータを取り扱うことから個人情報保護法や各種ガイドラインの遵守が厳しく義務付けられているが、そのための予算や人材は非常に限られている。そうした環境下にありながらも、最初の一歩を踏み出した、栃木県の那須赤十字病院の事例を紹介する。

生成AIが“見えないIT資産”を見つける救世主に?人に依存しないセキュリティマネジメント体制の整え方
DXの進展にともなって企業が抱えるアタックサーフェスは増え続けており、これらを人手で管理・対処していくのは限界を迎えつつある。そんな中、生成AIを活用することでASM(Attack Surface Management)や脆弱性診断を自動化・効率化するソリューションが注目を集めている。EnterpriseZine編集部主催イベント「Security Online Day 2025 秋の陣」に登壇したエーアイセキュリティラボの阿部一真氏は、そのような最新のWebセキュリティ対策の価値や効果、具体的な使用例などを紹介した。

Oracleラリー・エリソン氏が描く「すべてが変わる」AIの時代 熱弁された次世代ヘルスケアの全貌は
2025年10月13日から米国ラスベガスで開催されたOracleの年次イベントは、名称を「Oracle CloudWorld」から「Oracle AI World」へと変更し、「AI時代」の本格的な到来をあらためて宣言した。イベントで最も注目を集めたのは、同社 会長 兼 CTO ラリー・エリソン氏による基調講演。しかし、講演は急遽1時間開始が遅れ、ライブ中継形式に変更された。本人がステージにいない中継状態とはいえ、エリソン氏の講演は予定時間を超え、AI時代に変貌する“新たな世界”についての話題が尽きなかった。

なぜ企業は今、マスタデータ管理に本腰を入れるのか?──3年で4倍に拡大中のMDM企業CEOに訊く
AI導入で成果が上がらない企業が増える中、「根本原因はデータ品質にある」と指摘するのはマスタデータ管理(MDM)を提供するStibo Systemsだ。創業230年のデンマーク企業を率いるエイドリアン・カーCEOが来日し、「ゴミを入れればゴミが出る」というAI時代のデータ整理の重要性、日本市場で3年間で4倍の成長を遂げた同社の戦略について語った。MDM導入の壁から競合の動きまで、データ管理の最前線に立つ経営者の洞察を聞いた。
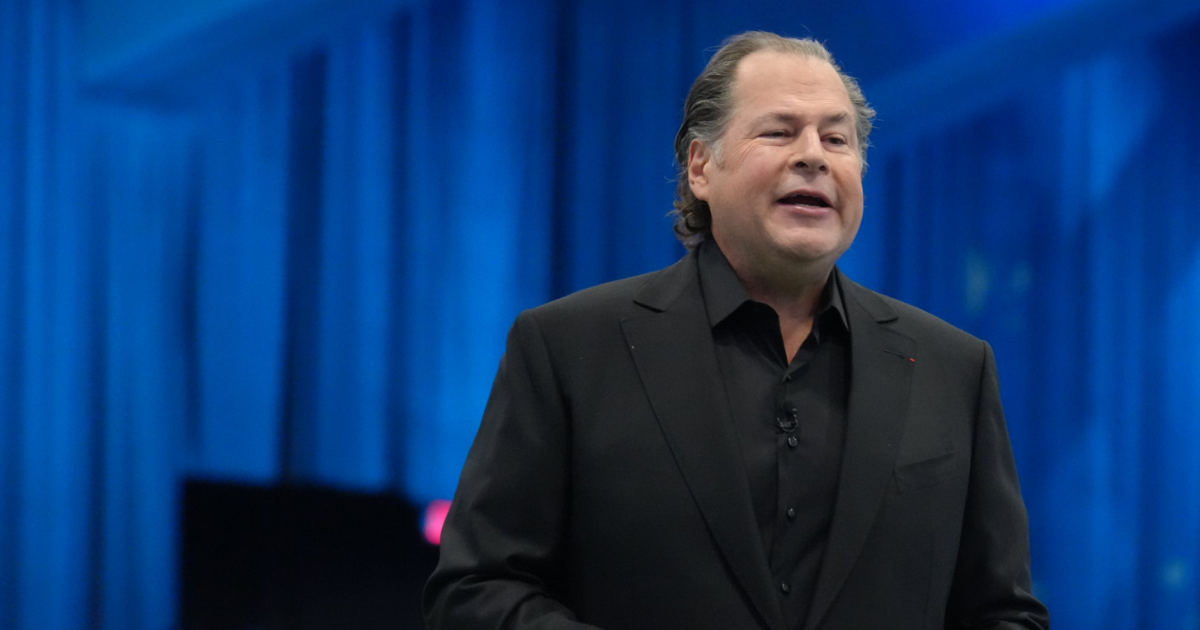
Salesforceが新たに掲げる「エージェンティック分断」解消のビジョン、Agentforceもさらに進化
現地時間10月14日、米Salesforce(セールスフォース)の年次イベント「Dreamforce 2025」がサンフランシスコで開幕した。ホストを務めた会長のマーク・ベニオフ氏は、新しいビジョン「エージェンティック エンタープライズ」を大きく打ち出した。

幕を閉じた大阪・関西万博、フランスパビリオン成功の舞台裏を支えた「バーチャルツイン」技術とは?
仏Dassault Systemes(以下、ダッソー)が、宇宙領域への取り組みを加速させている。同社は2025年9月10日、大阪府で行われた自社イベント「3DEXPERIENCE Conference Japan 2025」に合わせ、大阪・関西万博のフランスパビリオン内で、航空宇宙業界に特化したイベントを開催した。同社CEO(最高経営責任者)のPascal Daloz(パスカル・ダロズ)氏は、「航空分野で確立したバーチャルツイン活用を、宇宙開発にも拡大していく」と訴求した。

米国・公共機関のキーマンと考える、AIの進化との付き合い方──自律的であっても人間の確認は不可欠
公共機関でのAI活用は、どのように進めるべきか──そのヒントを探るべく、2025年6月に米国・ワシントンD.C.にて開催された「AWS Summit Washington, DC」における2つのパネルセッションに注目した。一つは、Amazonと米中央情報局(以下、CIA)の幹部が登壇し、AIがセキュリティにもたらす変化とリスクを語った「The intelligence edge: AI security strategies from Amazon and the CIA」。もう一つは、米財務省、テキサス州、Anthropicのリーダーたちが官民連携と公共サービスの革新を議論した「The AI (r)evolution: Meet the trailblazers transforming public service」だ。国家セキュリティから行政サービスまで、公共領域におけるAI活用の実例と課題、そして未来への示唆が詰まった議論をレポートする。
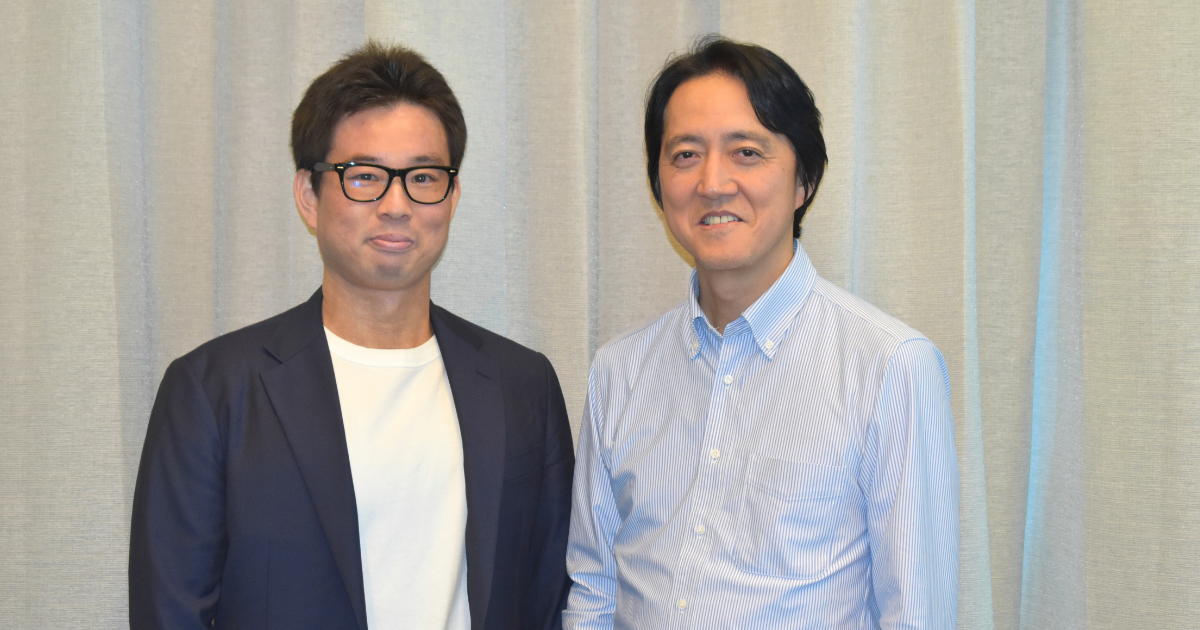
日本企業のSIer依存に潜むAI活用の落とし穴──Databricksの「データ+AI」戦略に迫る
米国時間6月9日から12日にかけて行われたDatabricksの年次イベント「Data+AI Summit 2025」には多くの参加者が訪れ、大盛況のうちに幕を閉じた。基調講演では様々な発表がなされたが、どの発表も一貫して、イベント名にもある「データとAI」にフォーカスされたものであった。今回は、発表された数々の新機能を踏まえ、各キーマンへのインタビューから見えてきた同社の戦略を改めて振り返る。

AI台頭で目まぐるしく変化する「次世代データ基盤」の要件──明日から使える実践的なアプローチを学ぼう
EnterpriseZineでは、11月7日(金)にオンラインイベント「Data Tech 2025」を開催。味の素や東京海上日動システムズ、関西電力などの企業のほか、データの情報発信を積極的に行う横山翔(ゆずたそ)氏といった有識者などが登壇し、「データ」に関する最前線の情報をお届けする。本記事では、イベントの見どころを紹介。進化の早いAI時代に押さえるべきデータ基盤構築・活用のポイントを、ぜひキャッチアップしていただければ幸いである。

SAPが新たなイベント「SAP Connect 2025」を開催 AI エージェントの方向性示す
米ラスベガス・現地時間10月6日から8日にかけて、SAPは新しい年次イベント「SAP Connect 2025」を開催した。同イベントは、ファイナンス、調達、サプライチェーン、HR、CX部門のリーダーたち相互の「Connect(つながり)」を深めることを目的に行われた、同社初の試みとなる。

音声AIで「電話体験」を変革する──IVRy奥西CEOが語る、対話型音声AIスタートアップの勝ち筋
AIによる自然な対話による顧客対応へ、音声AI変革を牽引するIVRy奥西CEO。ChatGPT登場前から生成AI時代の到来を予測し、音声データとアカウント数の蓄積に注力してきた。ハルシネーション問題をタスク分解で解決し、東横インやクレディセゾンなど大手企業での導入実績を積み重ね、音声データ解析から顧客インサイトを抽出する独自価値を確立。東横イン、クレディセゾンなど大手導入実績と世界に挑む戦略を同氏に聞いた。

freeeの社内AIチャットボット、月1万件の質問に自動回答──4,000ファイルのナレッジをGeminiで全社活用する仕組み
急成長企業が直面するナレッジ管理の混乱を、AIチャットボットで解決したfreee。月に約1万件の社内質問に応答する「わカルさんbot」の背景には、単なるAI導入を超えた組織的な取り組みがあった。同社の稲村氏が明かす、効果的なAIチャットボット構築の全貌とは。

生成AIで激変した「検索体験」ゼロクリック時代に求められるSEOからGEOへの転換
「生成AIツール」の日常生活への浸透は、検索エンジンのアルゴリズム理解に基づく“表層的”なSEO対策を過去のものにしようとしている。自社のWebサイトへのトラフィックが減ったと考え、顧客体験向上に向けた取り組みの方向性を見失っている企業にとって、AI由来のトラフィックを可視化することで、新しい最適化の方向性が見えてくる。

なぜオムロンは調達改革を実現できたのか? カテゴリーマネジメントで目指す持続可能なコスト最適化
オムロンが間接材調達改革でSAP Ariba導入を実現した。グローバルで154社を抱える同社は、過度なカスタマイズを抑制し「Fit to Standard」を徹底。現場の反発を和らげるため、コスト削減ではなく効率化を訴求する工夫を施した。カタログ化率46%、PO率63%を達成し、6つの重点品目でカテゴリーマネジメントに着手。前回の一過性削減の反省から、今回はルールと規律の強化により持続可能なコスト最適化を目指す。2025年8月6日開催の「SAP NOW AI Tour Tokyo & JSUG Conference」で佐々木正男氏が成果を報告した。

OpenAIやMetaなどのAIボットがWebインフラに大打撃 “悪質DDoS攻撃”の実態と防御策
AIボットトラフィックの急激な増加により、企業のWebインフラが危機的状況に陥っている。MetaやOpenAIなどのAIボットによる大量アクセスがサービス低下を招きかねない状況下、AI技術を悪用した高度な攻撃も登場したことで、従来の防御手法は限界を迎えている。この深刻な課題への対処法のひとつとして注目されているのが、エッジクラウドプラットフォームを活用した包括的な防御戦略だ。ファストリーのシニア チャネル パートナー セールス エンジニアである東方優和氏はEnterpriseZine編集部主催イベント「Security Online Day 2025 秋の陣」で、AI時代における最新の脅威動向と効果的な防御戦略について解説した。

大阪ガスが「Energy Brain」で実現したエネルギーマネジメントの自動化とAIエージェントによる次なる挑戦
大阪ガスが2023年8月に開始した遠隔AIエネルギーマネジメントシステム「Energy Brain」は、機械学習を活用したエネルギー需要予測により顧客の省エネを実現している。同システムの開発では機械学習の運用課題を、Google CloudやクラウドETLツールのTROCCOの導入により解決した。本記事では「気象予測」「データアナリティクス」「最適化計算」の3つの要素技術から、統合開発プラットフォームの構築、需要予測MLOpsの確立、そして今後のAIエージェント活用まで、Energy Brain成功の舞台裏を詳しく紹介する。

放送局での業務自動化に「Gemini」が大活躍──「AI関数」によるデータ分析/アプリ開発の民主化
Google スプレッドシートでデータをまとめ、AppSheetで業務アプリを管理する──こうした日々の業務の中で、「このツール自体が、もっと賢く手伝ってくれたら」と感じたことはないでしょうか。これまでは、私たちの指示を正確に実行するだけの「道具」だったアプリケーションが、Geminiの統合によって、私たちの意図を汲み取り、思考する「パートナー」へと進化を遂げました。本稿では、「Google スプレッドシートのAI関数」と「Gemini in AppSheet」を用いた業務自動化の新たな可能性を探ります。この連載はリレー形式でGoogle Cloud公式ユーザー会Jagu'e'rのメンバーがお届けしており、今回は民間の放送局でIT業務に携わる倉田が担当。自身の業務経験に基づき、放送局で起こりがちな具体例を交えながら、これらの機能をご紹介します。

カメラアクセサリー3,000点の需要予測を自動化したニコン:R&D部門が先導した柔軟な開発の舞台裏
カメラメーカーとして世界をリードするニコンは、約3,000点におよぶカメラアクセサリーの需要予測をAIで自動化することに成功した。人の“勘と手作業”に依存した業務フローから脱却したことで、カメラアクセサリー品目の99%をカバーする高精度な需要予測システムの構築を実現している。一筋縄ではいかなかったという同システムは、開発から実運用、改善のサイクルを同社の研究開発(R&D)部門だけで内製できているのが特徴的といえる。どのようにしてデータ基盤を整備し、自動化を実現したのか。取り組みを率いた2名のリーダーに話をうかがった。

なぜAI活用で部署間に温度差が生まれるのか、「組織の溝」を本質的に解消する方法
企業の「AI」導入が加速化する中、成功企業の「型」が徐々に見え始めています。それは、一体どのようなものなのでしょうか。連載『AI活用の真髄──効果的なプロセスデザインとビジネス変革』では、“業務コンサルタントの視点”でAI導入を支援している小坂駿人(パーソルビジネスプロセスデザイン所属)が、AIを「真のビジネス変革」につなげるためのポイントを5回にわたって解説。第4回は、AI担当部署と経営層、現場の連携について考えます。

なぜ企業の生成AI活用は思うように進まないのか? 「期待とのギャップ」を埋める対策──Gartnerアナリスト提言
なぜ企業の生成AI活用は思うように進まないのか? 2025年8月27日から28日に開催されたガートナージャパンの「デジタル・ワークプレース サミット」で、その理由が明らかになった。パイロット導入は進むものの、大規模展開への投資意向を示した企業はわずか17%。8割超の組織が価値を実感できずに停滞している背景にある課題と、その解決に向けた実践的アプローチを「デジタル・ワークプレースにおける生成AI活用戦略:4つの重要トレンド」講演から解説する。

日本は「プラスAI」から「AIファースト」へ変革が必須──IBMが富士通と見据える技術革新の未来図
日本アイ・ビー・エム(日本IBM)は9月17日に年次イベント「Think Japan」を開催した。イベント冒頭のキーノートでは日本IBM 代表取締役社長執行役員 山口明夫氏や富士通 代表取締役社長CEO 時田隆仁氏らが登壇し、富士通と日本IBMの協業や「IBM AI Lab Japan」を立ち上げる計画などが発表された。本稿ではその模様をレポートする。

教員がAIを欺いて学生の“ズル”を回避? 進化する「AI騙し」に対抗できる組織のセキュリティ強化術
生成AIやAIエージェントの活用気運が高まる中、そこに潜むリスクを認識し、組織として適切に対応するための体制を整えることは、AI活用に取り組むすべての企業にとって必須の課題です。連載「AI事件簿 ~思わぬトラップとその対策~」では、過去のAIに関するインシデント事例や先人たちの教訓をもとに具体的なリスク対策を解説しています。連載第5回となる本記事では、AIを騙すサイバー攻撃「プロンプトインジェクション」にフォーカス。生成AIを活用していると特に起きやすいこのリスクはどのようなもので、どう対策すべきなのでしょうか。

村田製作所が挑む「自律分散型DX」の現在地──80年の歴史に新たな基盤を築くDXリーダーの覚悟
製造業でDXを進めるにあたっては、「技術革新」と「組織変革」を両輪として進める必要性が多くの企業に認識されている。そうした中、村田製作所は長期構想「Vision2030」の実現に向けて、DXを経営の中核に据え、単なるシステム導入にとどまらない本質的な変革に挑んでいる。2022年から取材当時まで情報システム統括部の統括部長を務めてきた須知史行氏は、80年の歴史をもつ同社において、デジタル人材の育成とITインフラの整備を基盤に、自律分散型経営の実現を目指し、様々な取り組みの指揮を執る。進行中の基幹システム刷新プロジェクトやデジタル人材育成、製造業DXの展望について同氏に話を聞いた。

元楽天副社長 平井康文氏がRevCommに参画──音声AIの可能性、「人財」を軸にした組織変革へ
音声技術とAIを活用して、ビジネスコミュニケーションの課題解決に取り組むRevComm。同社は2025年7月1日、新たに取締役プレジデント&COO(Chief Operating Officer)として平井康文氏の就任を発表した。Ciscoや楽天で要職を歴任し、輝かしい実績を持つ平井氏。同氏がなぜ今、スタートアップであるRevCommに参画するのか。音声AIの未来に見出す可能性と、その戦略に迫る。

なぜMUFG、ソニー、セブン&アイはGoogleのAIを選んだのか?── Google Cloud幹部が語る日本企業との「共同のイノベーション」
MUFG、ソニー、セブン&アイといった日本の大手企業がGoogle Cloudを相次いで選択している。その背景には、Gemini 2.5をはじめとするAI技術、クラウド、データ基盤インフラが統合されたAIネイティブクラウドの統合性に対する高い評価がある。Google Cloud Next Tokyo 2025の2日目基調講演で紹介された先進事例と、Google Cloud幹部への独占インタビューにより、日本企業の導入の理由を明らかにしていく。

板倉弁護士が警鐘「今が意思反映の最後のチャンス」データ・AI関連の法改正で企業が押さえるべきポイント
個人情報保護法の3年ごと見直し、データ利活用法制の整備、AI法成立──。データ・AI関連の法制度が同時並行で整備される中、ひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士は「これらの法改正が、制度設計の段階で事業者の声を反映させる最後のチャンス」と警鐘を鳴らす。本稿では、2025年6月24日に開催された「Data & AI Conference『Trust 2025』」で行われた同氏のセッションの内容をお届けする。

国産SaaS連合が示したERPの「オフロード」という選択肢 SAPの“2027年問題”を解決できるか
多くの日本企業が「2025年の崖」や「SAPの2027年問題」という課題に直面し、レガシーとなった基幹システムの刷新を迫られている。複雑なアドオン開発に縛られて肥大化したERPから、いかにして脱却すべきか。その有力な解として、セゾンテクノロジーが主導する国産SaaSベンダーとの「ERPモダン化アライアンス」が始動した。iPaaS(Integration Platform as a Service)の「HULFT Square」を中核に、ERPのコア機能はそのまま、日本固有の業務要件をSaaSに「オフロード(切り出し)」する。この「ポストモダンERP」の考え方は、企業の俊敏性を高める一方、システム全体の設計が複雑化するリスクもともなう。そして、この新たなアプローチの成否の鍵を握るSIerの役割も考察した。
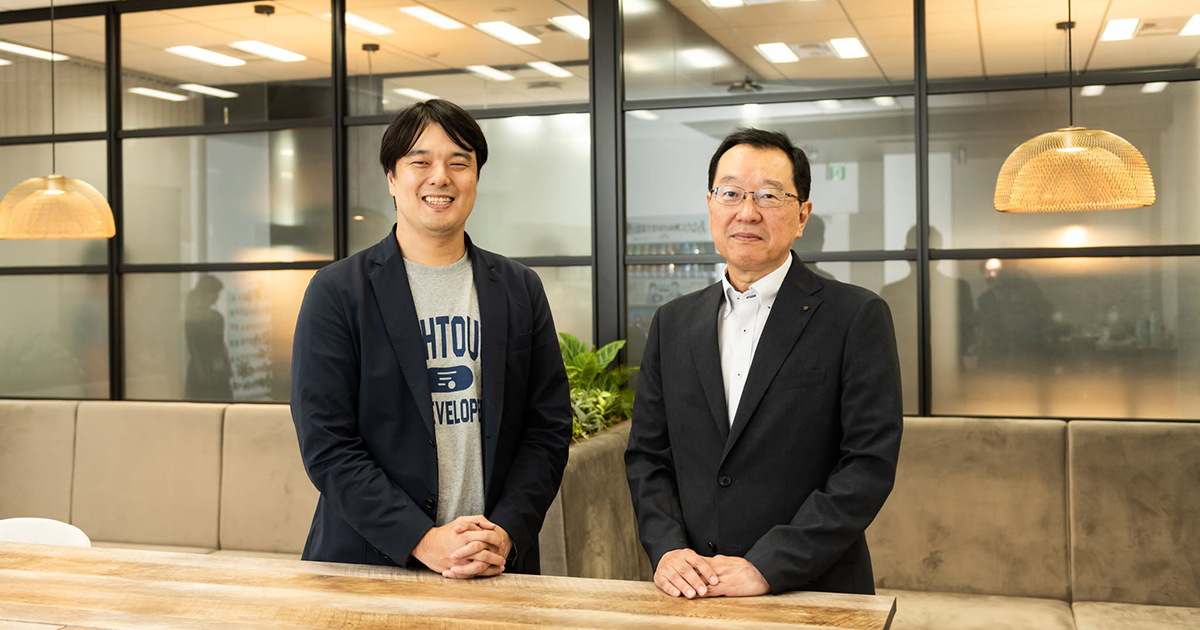
スズキ 鵜飼芳広×テックタッチ 井無田仲──グローバル企業が「中小企業型経営」で現場を動かす
2025年度から、新中期経営計画「By Your Side」を掲げたスズキ。2030年度に売上8兆円、営業利益8000億円を目指すスズキでは、DXは単なるIT改革を超え、企業文化そのものを進化させる力として位置付けられている。このDXの根底にあるのが「中小企業型経営」という独自の精神だ。グローバル企業でありながら、現場に近い判断や迅速な実行を重視する姿勢は、DXの進め方にも色濃く反映されている。どのように現場を巻き込み、全社的な変革を進めてきたのか。テックタッチCEOの井無田仲氏が、全社DX推進を担うシニアフェロー 鵜飼芳広氏に大胆な経営目標の裏側で進む、“DXの実像”について聞いた。

「弁護士のジレンマ」から生成AIで起業したLegal Agent朝戸氏 ──「士業スキル×AI」に勝ち筋を探る
ChatGPT-4oからGPT-5へとその進化はとどまることを知らず、あらゆる業界でゲームチェンジが起きている。中でも、膨大な知識と経験が求められる専門職の世界も例外ではない。法律業界もまた、人力に依存してきた従来のビジネスモデルが大きな転換期を迎えている。 今回お話を伺ったのは、新進気鋭の法律事務所「Legal Agent」代表の朝戸統覚氏。大手法律事務所での経験から、既存の法律業務のジレンマを痛感し、生成AIの可能性にいち早く着目。弁護士業務に特化したAIツールを自作し、人力の階層構造に依存しない新たな法律事務所を立ち上げた。起業を決意させた生成AIの衝撃、そして「士業のベテランスキル+AIが勝ち筋」と語る朝戸氏の描く法律業界の未来像とは何か。最前線で新たな生存戦略を実践する朝戸氏に、これまでの歩みと今後の展望を伺った。

「オンプレ資産」こそAIの金脈 相次ぐ買収で陣容を整えるCloudera、その勝算は
2025年8月7日、建国60周年を迎えようとする熱気に包まれたシンガポールで、Clouderaはフラッグシップイベント「EVOLVE25」を開催した。事前登録者数は1,000名超と盛況ぶりを見せる中、イベントのテーマに据えられた「Bringing AI to Your Data - Anywhere」を体現するような同社の競争戦略が示された。

AIが招いた大規模エンジニアレイオフの影響とIT採用市場の最新動向:打開策は“自組織らしさ”の確立?
連載「DX人材難のIT部門に捧ぐ『優秀な人材と自部門のマッチング法』」では、優秀とされるDX人材がどのような視点で転職する企業を選んでいるのかといった“採用”の視点から、自部門とDX人材のマッチング率を高める具体的施策を解説。DXを担当するDX部門やIT部門で人材採用に携わる、もしくは人材難に悩んでいる方に向けて、「採用」の視点からDXプロジェクトを成功させるヒントを届けます。連載最終回となる本記事では、AIがIT人材市場にもたらす影響と、その中で自組織が生き残るための具体策「ブランディング戦略」の立て方について解説します。

Google CloudのGemini CLIが実現する「バイブコーディング」── コード生成30%超の裏にあるReActループとMCPの強み
Google Cloudが推進するAIドリブンソフトウェア開発では、「ReActループ」と「MCP(Model Context Protocol)」が中核技術となる。今回は、自然言語からコードを生成する「バイブコーディング」、計画作成から実行まで自動化する「Gemini CLI」、外部ツールとの連携を可能にする「MCP対応」などの最先端手法について、Google Cloud Next Tokyo ‘25で来日した幹部に聞いた。

勝者はSalesforce、AI時代の主役は「データ」へ Informatica争奪戦で業界再編は?
生成AI、そして自律型エージェントAIの登場が、ビジネスを一変させようとしている。企業の競争優位性は、もはやアプリケーションの機能ではなく、その根幹を支える「データ」そのものへとシフトしている。この地殻変動を象徴するのが、SalesforceがIBMとの争奪戦の末に獲得した、データ管理のトップベンダー、Informaticaの一件だ。これは単なるM&Aではない。AI時代のデータ覇権を巡る、新たな戦いの幕開けといえる。この買収劇を起点に、今後の業界再編、企業が取るべき針路について考察してみた。

AIエージェント時代に浮上するデータの責任問題──「AIセーフティ」と「AIセキュリティ」という2つのリスクにどう対処するか
「人間100人、AI100人の組織構成を検討している」──そんな企業が既に日本に現れている。AIエージェントが業務の主要な担い手となる時代、データの責任範囲と権限移譲はどう再定義されるべきか。Quollio Technologies CEO 松元亮太氏と、シリコンバレーでAIセキュリティスタートアップの成長を牽引し、Ciscoによる買収を経験した平田泰一氏が語る、データ世界観の根本的転換とは。
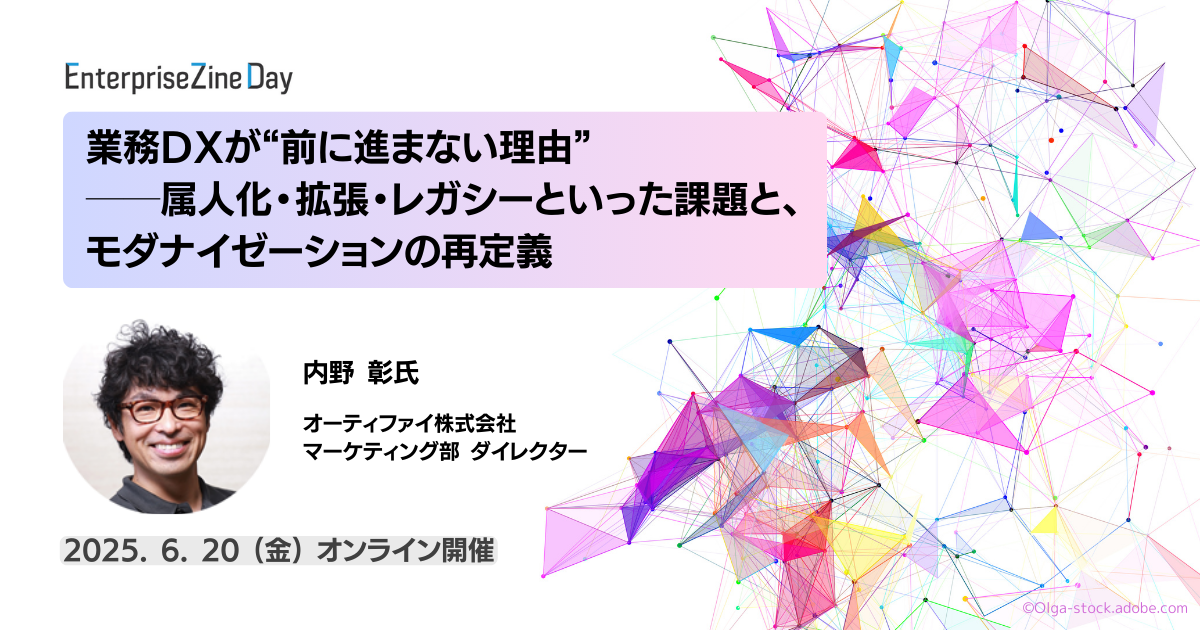
柔軟な開発か品質の確保か? アジャイル開発を活かせない企業に必要な“テスト自動化×AI”のアプローチ
2025年6月20日、EnterpriseZine編集部主催のオンラインイベント「EnterpriseZine Day 2025 Summer」が開催された。オーティファイ マーケティング部 ディレクター 内野彰氏による講演「業務DXが“前に進まない理由”──属人化・拡張・レガシーといった課題と、モダナイゼーションの再定義」では、多くの企業が現在直面する課題「DXの停滞」を解決するためのヒントが、「AI×開発・テスト自動化」という切り口から紹介された。

セールスフォースの「Agentforce 3」の真価:MCP、可視化、200超の業種別テンプレートで何が変わるのか?
セールスフォースが2025年7月に発表したAgentforce 3では、既存顧客からの要望を反映した3つの強化の柱が注目される。AIエージェントのパフォーマンス監視を可能にするCommand Center、Manufacturing CloudやFinancial Services Cloudなど200超のインダストリー特化型スキルテンプレート、そしてMCPサポートによる相互運用性の向上だ。AgentExchangeを通じた信頼性の高い外部連携や、自然言語によるガードレール設計も実現し、企業のビジネスポリシーに準拠したAIエージェント活用を推進する。

トヨタ自動車が構築を目指す「エッジAI分散基盤」とは?高度なモビリティAIの学習を阻む課題と突破口
トヨタ自動車は、エッジAI分散基盤の構築に本格的に取り組んでいる。高度なモビリティAIを実現するためには、膨大な車両データの効率的収集と、継続的なAI学習を支える大規模計算基盤が不可欠だからだ。2025年7月に開催された「F5 AppWorld 2025」(F5主催)で、同社の古澤徹氏は2つの技術的アプローチを紹介した。Wi-Fiとエッジサーバーを活用したデータ収集の効率化、そして再生エネルギーを活用した広域分散GPUクラスターによる学習基盤の構築だ。これらの実現に向け突破しなければならない課題と、同社が推進する活動とは何か。

多忙極める“AI時代”のセキュリティ人材育成、「効果的&リーズナブル」な施策は本当に存在するのか?
9月4日(木)~5日(金)の2日間にわたり開催される、EnterpriseZine編集部が主催する年次カンファレンス「Security Online Day 2025 秋の陣」。本稿では、その見どころを紹介する。CIO/CISOからエンジニアまで、IT部門/情報システム部門に所属する方から経営層の方まで、そして大企業から中堅・中小企業まで、立場や職種ごとの目線・事情に合わせてサイバーセキュリティの課題・ノウハウに斬り込む講演が盛りだくさんだ。

IT部門は消滅する?大規模開発の常識を覆しかねない自律型AIエンジニア「Devin」のインパクトとは
2025年5月、ウルシステムズは米Cognition AIと戦略的パートナーシップを締結し、自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」の国内エンタープライズ市場への展開を発表した。同社は、2025年1月からDevinを自社導入して活用してきた結果、その可能性を高く評価したためパートナーシップ締結に至ったという。では、Devinの登場がビジネスにもたらすインパクト、ひいてはSI産業全体に及ぼす影響はどれほどのものなのか。ウルシステムズの取締役副社長でテクノロジー部門を統括する桜井賢一氏に聞いた。

ガートナーが明かす「AIセキュリティ6大脅威」 なぜAIエージェントが機密情報を漏洩させるのか?
企業が信頼するAIが、実は機密情報を漏洩させる危険性を秘めている。ガートナーは、2025年7月に開催した「ガートナー セキュリティ&リスク・マネジメント サミット」で、データ損失、プロンプトインジェクション、出力リスク、データポイズニング、検索リスク、AIエージェントリスクという6つの脅威を明かした。アナリスト デニス・シュー氏がインタビューで、これらの脅威と対策について解説した。

AI時代のデータ活用はどこまでOK?個人情報保護委員会/デジタル庁の視点から学ぶ、企業が今すべきこと
デジタル経済の進展とAI技術の急速な発達により、世界各国でデータ活用が競争力の源泉となるなか、日本のデータ政策も大きな転換点を迎えている。2025年6月24日にAcompanyが主催したカンファレンス「Data & AI Conference Trust2025」では、個人情報保護委員会事務局 審議官の小川久仁子氏、デジタル庁 企画官の石井純一氏、Acompany 執行役員の竹之内隆夫氏が登壇し、データ活用と保護の両立について議論した。本稿では、個人情報保護法改正、DFFT(信頼性のある自由なデータ流通)の国際展開、データセキュリティ、プライバシー強化技術の内容を紹介する。

荏原製作所に新しい風を巻き起こす“精鋭集団”──3つの生成AIモデルを使い分けできる専用ツールを内製
113年の歴史を持つ荏原製作所で、急速にDXが進んでいる。多様な人材が集まるデータストラテジーチームでは、デジタルトリプレットなどを活用した製造DXや、脳科学をベースとした技術開発など、ユニークな視点からの試行錯誤が始まっている。生成AI分野では、ChatGPT、Claude、Geminiの3つのモデルを使い分けできる生成AIプラットフォーム「EBARA AI Chat」を内製開発。伝統的製造企業における生成AI活用と内製開発の裏側を、データストラテジーユニットリーダーとしてけん引する田中紀子さんに聞いた。

現場に根付いた「カイゼン文化」を管理間接部門でも──矢崎総業が生成AI活用で重視する“利益追求”
いよいよ伝統的な製造業でも生成AIは無視できない存在となっている。創業84年の老舗製造業・矢崎総業では、2024年に全社23万人を対象に独自の生成AI基盤「Y-Assistant」を構築・導入し、管理間接部門の生産性向上を推進している。「Givery Summit 2025 - AI Enablement Day」に同社 情報システム統轄室 システム技術評価部長の小池伸幸氏が登壇。製造業における生成AI活用の取り組みをギブリー執行役員 長目拓也氏と語った。


