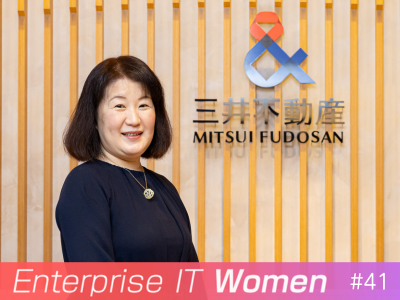会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- 何かがおかしいセキュリティ連載記事一覧
-
- 最近よく聞く「ゼロトラスト」の謳い文句は鵜吞みにして大丈夫?原点に立ち返り、本質と目的を見...
- そのセキュリティ製品は自社にとって本当に必要か?真に対策すべきリスクを分析・把握する手順を...
- クラウドセキュリティ界隈の疑問──「クラウドの“設定ミス”」という表現は適切か? 問題の本...
- この記事の著者
-

伊藤 吉也(イトウ ヨシナリ)
2022年より、米国本社の日本支社であるフォーティネットジャパン合同会社にて全国の自治体、教育委員会向けビジネスの総括を担当。専門領域は、IPAの詳細リスク分析+EDC法による対策策定。ISC2認定 CISSP、総務省 地域情報化アドバイザー、文部科学省 学校DX戦略アドバイザー、デジタル庁 デジタ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア