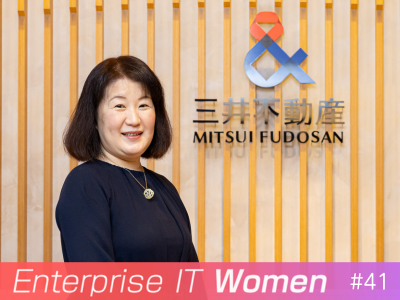総務省が「AIを守る/AIで守る」の2視点で進めるセキュリティ政策 生成AIで拓く新たな防御の可能性
攻撃者は作業コストを95%以上も削減している? 脅威にAIで立ち向かうために
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- Security Online Day 2025 秋の陣 レポート連載記事一覧
-
- 総務省が「AIを守る/AIで守る」の2視点で進めるセキュリティ政策 生成AIで拓く新たな防...
- セキュリティ人材不足でもSIRT組織は作れる! 鍵は橋渡し役「1.5線」の仮想組織
- 「敵を知って己を知る」──悪用厳禁の“ハッキングデモ”から攻撃者に与えている侵入の隙に気づ...
- この記事の著者
-

伊藤真美(イトウ マミ)
フリーランスのエディター&ライター。もともとは絵本の編集からスタートし、雑誌、企業出版物、PRやプロモーションツールの制作などを経て独立。ビジネスやIT系を中心に、カタログやWebサイト、広報誌まで、メディアを問わずコンテンツディレクションを行っている。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア