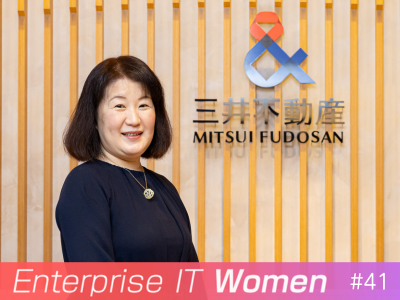Santenと日本ハムはマイクロソフトの生成AIツール導入でどう変わった?──研究/開発での活用に脚光
「Microsoft AI Tour Osaka」レポート
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
-
- Page 1
-
- Page 2
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

三浦 優子(ミウラ ユウコ)
日本大学芸術学部映画学科卒業後、2年間同校に勤務。1990年、コンピュータ・ニュース社(現・BCN)に記者として勤務。2003年、同社を退社し、フリーランスライターに。IT系Web媒体等で取材、執筆活動を行なっている。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア