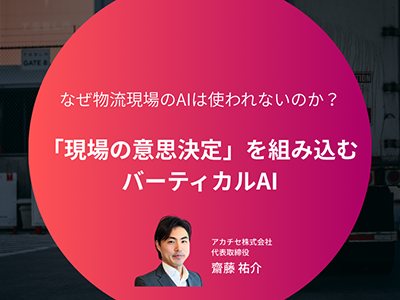生成AI活用が根付いたJTCのシステム部門は何をしたか?攻めの組織変革に有効な「バイブコーディング」
第8回:「変化に後から気づく」から「変化を先取りする」組織へ変革を

多くの日本企業、特に規模の大きな日本の伝統的企業「JTC(Japanese Traditional Company)」では、生成AIの活用に関する議論が進む一方で、実際の変革は思うように進んでいないケースが少なくありません。その原因の多くは技術そのものではなく、マインドセット、組織体制、開発プロセス、人材といった“非技術的な構造”にあります。連載「住友生命 岸和良の“JTC型DX”指南書」では、筆者が住友生命保険での実務経験をもとに、JTCの変革に必要な視点を解説してきました。第8回となる本稿では、生成AI時代に必要な「マインドの見直し」「組織体制の変革」「システム開発の効率化」「人材キャリアパス」について考えます。
生成AI時代に必要なマインドセットと組織の在り方
従来のJTCで新たにシステム開発を行う際には、「事業部門が要件を出し、システム部門が作る」という役割分担が当たり前でした。システム部門はシステムの安定稼働を保つ役割を果たし、事業部門はビジネスサイドとして構想を担う。しかしこの分業は、生成AI時代にはスピードと柔軟性の面で大きな課題があります。
変化が早く、ユーザー体験の改善サイクルが短い今の時代、「要件を固めてから着手する」というやり方では、プロジェクトが動き出す前に市場環境が変わってしまうことも珍しくありません。今の時代に必要なのは、「終わるまで待って開発する」方法ではなく、「ラフに開発して素早く試す」方法への転換です。完璧な要件を待つのではなく、素早く、小さく動かしながら進めることを組織全体に根付かせる。これが生成AI時代においてシステム部門に必要なマインドといえます。
“ラフに開発して素早く試す”ことができる組織に変わっていくためには、事業部門とシステム部門それぞれ数人を抜擢した“混成チーム”による共創体制を組むことが有効です。
そして、ここで注目すべきは“上流工程”の変革。事業部門が自ら生成AIを活用してバイブコーディング(Vibe Coding)に取り組み、素早く試作品(プロトタイプ)を作ることができる体制の整備が重要になります。
一般的にバイブコーディングとは、生成AIと対話して試行錯誤しながらコーディングを進めていくことを指しますが、実はこの仕組みは、JTCのシステム開発工程全体にも応用できるのです。
たとえば、上流工程では事業担当者が生成AIを活用し、頭の中のアイデアを形にします。画面や機能の試作時に生成AIを活用することで、紙の要件書を作る前に“目に見える形”でイメージを関係者と共有できるため、認識のズレを早めに解消できることが利点です。特にJTCでは、長期化しやすい要件定義の工程やベンダー調整の初期段階に生成AIを活用することで、意思決定のスピードと精度を高め、開発期間全体を短縮できる可能性を秘めているのです。
一方、下流工程では上流工程で具体化した内容をインプットとして、生成AIを活用しながら品質の高い実装に仕上げる開発体制を構築できます。ただし、生成AIは作業を効率化しますが、あくまでツールなので、品質保証、テスト、運用設計などの領域は人の知恵と経験が欠かせません。人とデジタルの融合開発から始めることがベストだと筆者は思います。
上流工程と下流工程の連携を、事業部門とシステム部門の混合チームによって一気通貫で進められるような体制を構築することが理想的です。そのために必要なことは、マインド・体制・ルール・ガバナンスのアップデート。ここに踏み込めるかどうかが、生成AI時代におけるシステム開発工程効率化の成否を決めるのです。
根強く残る「ウォーターフォール思想」どう変えていく?
多くのJTCがアジャイル開発を試したり、一部のシステムで採用したりしているものの、いまだに基幹系システムには従来のウォーターフォール型が根強く残っています。ウォーターフォール型では、要件をまとめ、数年かけてシステムを完成させる流れが一般的ですが、先ほども言及した通り、このスピードで進めていては、システム完成時には技術も市場も次のフェーズに進んでしまっています。結果として、関係者が多岐にわたることで認識の齟齬が発生しやすくなり、「上流工程の手戻り」問題が起きてしまうのです。
ここで必要なことは、「上流工程に手戻りがあることを前提とした思想」への転換です。バイブコーディングによって事業部門が迅速に試作品を作成し、それを混成チームで実装・改修・改善していく。実証実験を短いサイクルで回し、学びながら前進することが今後より必要になっていくでしょう。ここに生成AIのバイブコーディングが役立ちます。
この記事は参考になりましたか?
- 住友生命 岸和良の“JTC型DX”指南書 ~停滞するデジタル変革に喝!~連載記事一覧
-
- 生成AIが要件定義の在り方を変えるとき、情シスがすべきこと──“守りの要諦”として担うべき...
- 生成AI時代に“技術特化人材”は不要? 事業とITをつなぐ「CoE型人材」を育成する3のメ...
- 生成AI活用が根付いたJTCのシステム部門は何をしたか?攻めの組織変革に有効な「バイブコー...
- この記事の著者
-

岸 和良(キシ カズヨシ)
住友生命保険相互会社 エグゼクティブ・フェロー デジタル共創オフィサー デジタル&データ本部 事務局長住友生命に入社後、生命保険事業に従事しながらオープンイノベーションの一環として週末に教育研究、プロボノ活動、執筆、講演、趣味の野菜作りを行う。2016年から...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア