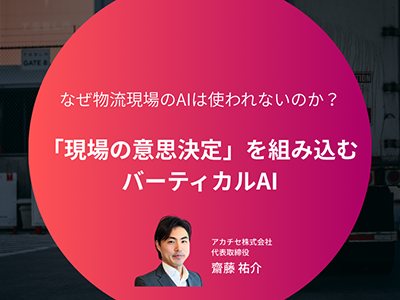生成AI活用が根付いたJTCのシステム部門は何をしたか?攻めの組織変革に有効な「バイブコーディング」
第8回:「変化に後から気づく」から「変化を先取りする」組織へ変革を
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- 住友生命 岸和良の“JTC型DX”指南書 ~停滞するデジタル変革に喝!~連載記事一覧
-
- 生成AIが要件定義の在り方を変えるとき、情シスがすべきこと──“守りの要諦”として担うべき...
- 生成AI時代に“技術特化人材”は不要? 事業とITをつなぐ「CoE型人材」を育成する3のメ...
- 生成AI活用が根付いたJTCのシステム部門は何をしたか?攻めの組織変革に有効な「バイブコー...
- この記事の著者
-

岸 和良(キシ カズヨシ)
住友生命保険相互会社 エグゼクティブ・フェロー デジタル共創オフィサー デジタル&データ本部 事務局長住友生命に入社後、生命保険事業に従事しながらオープンイノベーションの一環として週末に教育研究、プロボノ活動、執筆、講演、趣味の野菜作りを行う。2016年から...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア