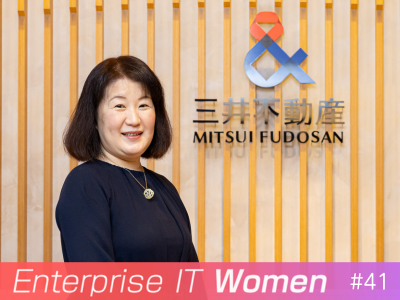Santenと日本ハムはマイクロソフトの生成AIツール導入でどう変わった?──研究/開発での活用に脚光
「Microsoft AI Tour Osaka」レポート

日本マイクロソフトは2025年9月、大阪にて「Microsoft AI Tour Osaka」を開催した。様々な業界での生成AI活用事例が紹介された中から、本稿では参天製薬(以下、Santen)と日本ハムの取り組みに注目する。単に生成AIを導入するだけでなく、それぞれの業務特性や企業文化に合わせた活用を模索し、成果につなげている点はきっとヒントになるだろう。
Santen:複雑な質問をする研究者の「壁打ち」でも利用
Santenは、2025年度~2029年度の中期経営計画における成長戦略で、眼科領域に特化したグローバルカンパニーとして、製品開発と収益の確保でグローバル成長を追求することを掲げている。Santen Digital & IT本部 Global Digital Innovation部 部長の武末有香氏は狙いを次のように説明した。
「Santenには130年の歴史があり、長きにわたり目の健康維持・増進を追求してきた。2035年に向けたビジョンとして、強みの相乗効果を生み、効果的に成果につなげるための組織能力を実現する『Santen Commercial Excellence』を軸に、世界の患者さんと眼科コミュニティから信望を集める眼科のリーディングカンパニーとなるという目標を掲げている。
その実現を前に、2025年度~2029年度までの中期経営計画を2025年春に発表した。Santenのビジネスモデルをすべての地域で強化し、市場をリードする企業としての信望を集めるべく、持続的な成長基盤の確立を目指している」(武末氏)

同社の成長のドライバーとなるのが「人材・組織」と「デジタル・IT活用」の強化だという。特に人材は最重要アセットと位置付け、能力向上とそれを活かす組織作りを進めている。社内のビジネスレイヤーに応じたデジタル活用を進めるべく、全社のIT・セキュリティ基盤を強化する方針だ。

様々な取り組みが進む中でも、生成AIに寄せる期待は大きい。Santenでは、次の4つの戦略的な枠組みのもと活用を推進しているという。
- 汎用生成AIサービス:ChatGPTに代表される汎用生成AIを導入し、全社員が日常業務で安全に活用できる環境を整備して、業務効率と創造性を高める
- Microsoft 365 Copilot:オフィス業務を担う社員にMicrosoft 365 Copilotを導入し、会議やメール、分析や資料作成を効率化。Microsoft 365に集約された情報を活かして業務の質を高め、生産性と創造性を向上させる
- 社内データやシステムに連携した生成AIサービス:既存の生成AIを社内データやシステムと安全に連携し、汎用AIでは得られない企業固有の文脈に沿った高精度な回答を実現。さらにAI Agentによる自律的な自動化と市民開発を推進し、AIを民主化して組織の生産性と競争力を飛躍的に高める
- 特定業務に特化したモデルを用いた生成AIサービス:特定業務に最適化したAIモデルやAI Agentを開発、または外部サービスを導入し、専門業務の自動化と精度向上を実現。ナレッジ継承や規制対応を支援し、業務プロセスを革新する
4つの枠組みのうち(2)は、2025年の初め頃から段階的に導入を開始。オフィスワーカーが日常的に使っているMicrosoft 365とシームレスにつながっていることで、自然と活用が進んでいるという。武末氏は「先行で20%の社員に導入したところ、Copilotの活用率は約98%で、ほとんどの社員が利用している状況。マイクロソフトさんからの指標によると、平均で週5時間ほど利用していることになる。私含め、社内からはCopilotなしの仕事スタイルには戻れないという声も挙がっているほど」と導入による手応えを語った。
汎用的な利用に加え、より業務に特化した(3)についても導入準備が進められている。
「(3)は、もう少しビジネスニーズに特化した生成AI活用になる。たとえばセールスや開発者、HR向けなどで、目的に合わせて検索出来るナレッジ・RAGを使っていけるような仕組みを2025年後半から進めていく計画だ。既に一部でパイロットを実施しており、より自分たちが使いやすい仕組みを開発していきたい。将来的には市民開発も視野に入れている」(武末氏)
専門性の高い使い方として、研究開発部門での利用例が紹介された。6年間、同部門に在籍した経験をもつ、 Santen Digital&IT本部 Global Digital Innovation部 Digital Solutionチーム 生成AIプロダクトマネージャーの大東達也氏は、部門の特性について次のように話す。
「研究者というと実験している姿をイメージする人も多いと思うが、実は文献調査、文書作成、データ分析、さらに会議、メール業務といった、いわゆるオフィス業務が大きな割合を占めている。私自身も研究部門に所属していたときは、オフィス業務の割合の多さに驚いた」(大東氏)

参天製薬株式会社 Digital&IT本部 Global Digital Innovation部 Digital Solutionチーム
生成AIプロダクトマネージャー 大東達也氏
文献調査、文書作成などの業務はこれまで利用してきたMicrosoft 365と親和性が高く、それだけでも導入効率が見込めるという。
「オフィス業務にCopilotを活用することで、研究者が本来やるべき創造的なタスクに時間を作っていくことができるのではないかと期待の声が挙がった。実際に4月にテスト導入したところ、研究所の責任者も高評価で、研究者用ライセンスを一括購入した」(大東氏)
データ化されていなかった紙の休眠資料もデジタル化して活用していくことになったが、紙の図や表を正確に取り込むのは課題として挙げる。
続けて、Copilotの機能が進化していくなかで、大東氏がとくに評価している2つを紹介した。
「1点目は検索。Copilotで検索を行う場合、社内のものすべてから検索を行うため、どうしても検索精度が下がるという課題があった。対策を考える中で、RAG構築するといいのではという案も出ていたが、ある日、Copilotの新機能としてSharePoint エージェントが登場。検索対象をプロジェクトごとや部署ごとなどに分けることができるようになり、精度が改善された」(大東氏)
2点目として挙げられたのはリサーチツール。複雑な調査や情報収集を専門的に行うことができる研究者向けの「Researcher」と「Researcher エージェント」が役に立っているという。
「当初は、いわゆる科学的な推論や高度な文献調査にCopilotを利用するのは厳しい状況だった。推論を行う場合、『aとbを混ぜて、そこにcを加えるとどうなる?』といった問いかけを行うと、複雑な問いのために『わかりません』となってしまうことが多かったからだ。ところが、ResearcherとResearcher エージェントによって複雑な質問への答えもできるようになった。思考の相棒として利用できるものに変化している」(大東氏)
思考を明確にするために、いわゆる「壁打ち」として生成AIを利用する人は多いが、より複雑な質問をする研究者も利用できるようになったということだろう。1日300件くらいの論文タイトルを調べる文献作業でも、Researcherを利用すると、作業時間は従来の半分程度と明かした。
大東氏は、Copilotを採用した理由としてセキュリティ面を挙げる。
「他の生成AIでも同じようなことはできるが、社内の研究データが外部流出する危険があるため、他の生成AIツールは使わないように研究部門のスタッフにお願いしている」(大東氏)
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

三浦 優子(ミウラ ユウコ)
日本大学芸術学部映画学科卒業後、2年間同校に勤務。1990年、コンピュータ・ニュース社(現・BCN)に記者として勤務。2003年、同社を退社し、フリーランスライターに。IT系Web媒体等で取材、執筆活動を行なっている。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア