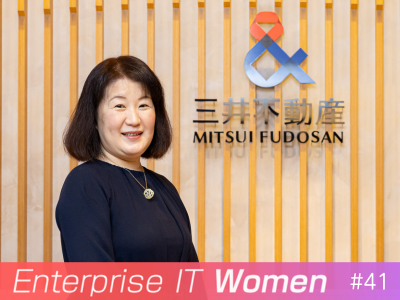会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- バックオフィスDX連載記事一覧
-
- 沢渡あまね☓ワークフロー総研 対談#02:ポストコロナ時代のIT部門はITサービスマイスタ...
- 沢渡あまね☓ワークフロー総研 対談#01: ポストコロナ時代の組織はオープン型へ舵を切れ
- 今年こそバックオフィス改善に向けた潮目が変わる――マネーフォワード 成末さん
- この記事の著者
-

加山 恵美(カヤマ エミ)
EnterpriseZine/Security Online キュレーターフリーランスライター。茨城大学理学部卒。金融機関のシステム子会社でシステムエンジニアを経験した後にIT系のライターとして独立。エンジニア視点で記事を提供していきたい。EnterpriseZine/DB Online の取材・記事も担当しています。Webサイト:https://emiekayama.net
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア