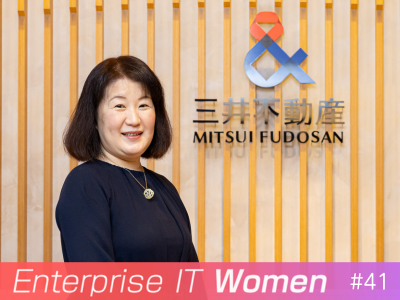AI活用でアタックサーフェスが急拡大……新脅威に打ち勝つ「プロアクティブセキュリティ」実現の3要素
ディープフェイク詐欺で約38億円の被害報告も 最新の脅威動向と、先を見据えた対策の重要性を解説
企業のセキュリティ部門が運用するツールは平均40個、根深い“ツール管理複雑化”の課題
攻撃者の悪用事例も報告される一方、企業でのAI活用も加速している。生成AIをはじめとしたデジタル活用の拡大によって、企業のアタックサーフェス(攻撃対象領域)は爆発的に拡大している。従来のレガシー環境中心の攻撃対象から、生成AIとAIOps、クラウドネイティブアプリケーション、IT/OT環境統合、SaaSアプリの急増、ソフトウェアサプライチェーン、さらには人的要因まで、攻撃者にとっての機会が多層構造で無数に存在している。
岡本氏は、アタックサーフェスの拡大にともない企業が直面している問題を3つの数値で示した。まず1つ目が、世界の75%の組織が年1回以上ランサムウェア攻撃を受けているということ。2つ目は、サイバー攻撃の被害にあった組織の70%が、未管理の状態でインターネットに公開している資産が侵害の原因となっていることだ。3つ目は、トレンドマイクロが対応したインシデントの52%がフィッシング起因だったことである。

これらの現実における根本的な問題は、「見えない資産は守れない」ことにある。多くのセキュリティ部門では、セキュリティを中心に多くのツール(CASB、IPS、ファイアウォール、EDR、EPP、各種クラウドアプリ、認証システムなど)を使用している。その数は、平均して40個にものぼるという。これにより、“ツール管理の複雑化”という新たな課題が生じてしまい、解決の糸口が見えないと悩んでいる方も多いのではないだろうか。
上記に加え、人材不足の加速も深刻な問題だ。一説によると、日本のセキュリティ人材は2023年時点で約11万人が不足しており、需要と供給のギャップは拡大の一途をたどっている。
多数のツールを駆使したセキュリティ分析・運用は、人材不足の問題を考えると非現実的といえる。この課題に対し、岡本氏は従来のリアクティブ(攻撃後対応)中心の対策から、プロアクティブ(攻撃前対策)中心の対策にも注目する必要性を説いた。
現在のセキュリティ投資配分を分析すると、根本的な問題が浮き彫りになってくる。防御(35~40%)、検知(25~30%)、対応(15~20%)といったリアクティブな対策に70~90%の投資が集中している一方で、攻撃を受ける前にリスクを特定・軽減する予測領域への投資は5~10%と極めて少ない。

「どこから攻撃されるのか、どんな経路で攻撃者が入ってくるのかを予測し、攻撃を受ける前に潰し込む“プロアクティブ”な対策をとることで、万が一に備えるリアクティブな対策を効率化することができます。この視点が、意外と欠けてしまっているのではないでしょうか」(岡本氏)
この記事は参考になりましたか?
- Security Online Day 2025 秋の陣 レポート連載記事一覧
- この記事の著者
-

森 英信(モリ ヒデノブ)
就職情報誌やMac雑誌の編集業務、モバイルコンテンツ制作会社勤務を経て、2005年に編集プロダクション業務とWebシステム開発事業を展開する会社・アンジーを創業した。編集プロダクション業務では、日本語と英語でのテック関連事例や海外スタートアップのインタビュー、イベントレポートなどの企画・取材・執筆・...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
提供:トレンドマイクロ株式会社
【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア