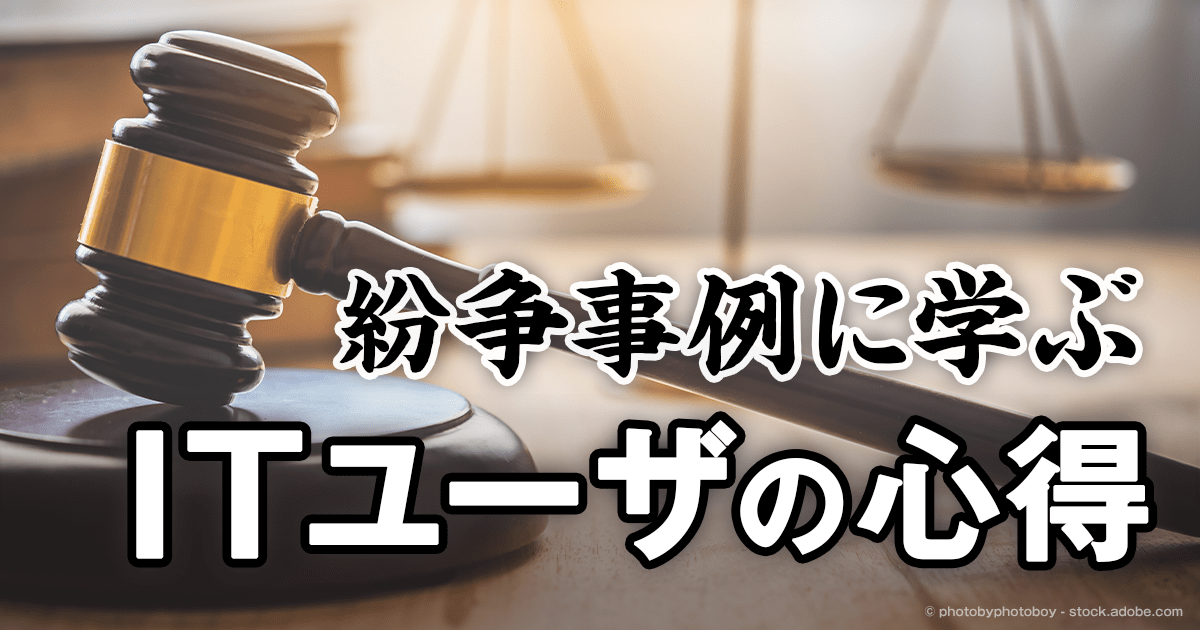
本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム開発の委託でよくある『準委任契約』の落とし穴、プロジェクト破綻時の責任は誰が負う?」です。システム開発を外部ベンダーに委託する際、“準委任契約”の形を取ることはそう珍しくないケースです。ただしこの場合、ベンダー側に必ずしも「システムを完成させなければならない」責任があるわけではないことに注意しましょう。どういった点に気を付ければよいのか、ある判例をもとに考察します。
準委任契約で起こる「完成義務」の問題
システム開発を外部ベンダーに委託する際、いつ何時でもベンダーがシステムの完成責任を負うわけではないことは、この連載の読者の皆さんならご存じでしょう。準委任契約などで開発プロジェクトを行う場合は、原則としてベンダー側に完成義務はありません。
ただ、準委任契約でさえあれば例外なく完成責任はないのかといえば、そんなこともありません。たとえば、成果物の納入を条件とする準委任契約もありますし、準委任の原則などとは関係なく、双方が完成を約束するようなプロジェクトは山のように存在します。
危険なのは、双方がこのあたりの確認をせず、ベンダー側が準委任だからと勝手に「完成責任はない」と判断したり、逆に発注者であるユーザーが「システム作りは完成させなければ意味がないのだから、完成させて当然」と思い込んでしまったりすることです。
今回は、そんな裁判の事例を紹介します。準委任契約ではあるのものの、ベンダーは提案段階からシステムの完成を約束するかのような言葉を発注者に伝えていたようです。さて、このあたり裁判所はどのように判断したのでしょうか。事件の概要から見ていただきましょう。
東京高等裁判所 令和3年4月21日判決
ユーザー企業は自社の基幹業務を支える新システムの開発を企図し、大手ITベンダーに提案を依頼したところ、ベンダーからはシステム稼働の目標時期を記した提案書が示され、プロジェクトはスタートすることとなった。
新システムの開発は要件定義、基本設計、詳細設計、開発、テストといった工程ごとに個別の契約を締結する形で行うこととし各契約はその都度仕様書等に基づいて取り交わされていた。一方で契約書には、システムの完成時期について記載がなかった。
その様な状態で始まった開発は難航し、ユーザーからの追加要望や仕様変更が頻繁に発生するなどしてスケジュールの遅延が重なった。ベンダーはその都度対応を行ったが最終的にシステムの安定稼働には至らず、ユーザー側はプロジェクトの中断を決断し、ベンダーに対しシステムが完成していないことを理由に契約の解除と損害賠償を求めて提訴した。
(出典:裁判所ウェブサイト 事件番号 平成31(ネ)1616)
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア


























