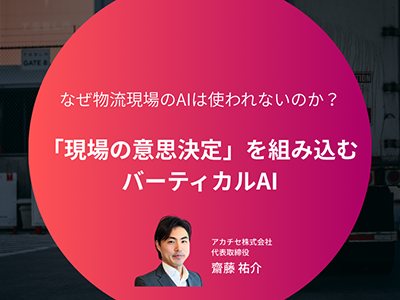会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

吉村 哲樹(ヨシムラ テツキ)
早稲田大学政治経済学部卒業後、メーカー系システムインテグレーターにてソフトウェア開発に従事。その後、外資系ソフトウェアベンダーでコンサルタント、IT系Webメディアで編集者を務めた後、現在はフリーライターとして活動中。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア