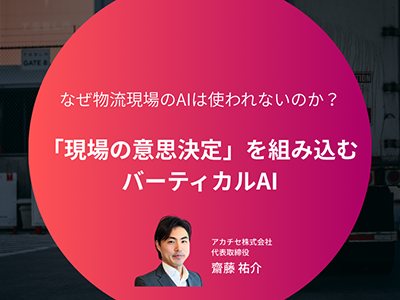イノベーションに効く洋書01:“Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs” 後編
(第2回)
自社のイノベーションを実現する「10の型」の総仕上げ
(4)これまでの結果を組み合わせる
ここまで長々と書いてきたことを、ここで組み合わせます。もう一度確認すると、
- 変化の方向:「10の型」のうち、どの要素に注力するかを見極める
- 強さのレベル:「10の型」のうち、いくつの要素に取り組むのかを見極める
- イノベーションの「変化の方向」「強さのレベル」から実践時の「イノベーション戦術」を選択する
この3つを組み合わせることで、自社のイノベーションを実現するための具体的な取り組みを行っていくことになります。
まとめ
今回紹介した“Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs”は、具体的なケースや手法が満載の非常に濃い一冊でした。冒頭での「10の型」の紹介にはじまり、それ以降、他社を分析する際にも、業界全体を分析する際にも、そして自社のイノベーションを検討する際にも、ひたすらこの型に基づいて考えていくという一貫性はわかりやすいですね。一方で、これだけ微に入り細に入り、さまざまな観点からイノベーションの検討を行ったとしても、この「10の型」を使って検討したプランを実現するためには、途方もない労力がかかるということがわかります。しかも、必ずしもその労力が報われるわけではない。
私が代表を務める株式会社スタイリッシュ・アイデアでは、プロダクトマネジメントを専門としています。その観点から本書を見た場合、多くの日本企業にとって重要な指摘は、製品だけのイノベーションでは、もはや持続可能ではないということでしょう。技術力を駆使して、これまでよりも薄くて軽い製品を作っているのに、どうして市場をひっくり返すほどのインパクトを与えられないのか。そのヒントを考えるために、「10の型」をもう一度眺めてみると良いかもしれません。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

新井 宏征(アライ ヒロユキ)
SAPジャパン、情報通信総合研究所を経て、2013年よりプロダクトマネジメントに特化したコンサルティング会社である株式会社スタイリッシュ・アイデアを設立。2006年に『プロダクトマネジャーの教科書』を翻訳出版後、企業に対するプロダクトマネジメントの導入や新規事業開発、製品開発の支援を行っている他、「プロダクトマネジャー養成講座」を開講し、プロダクトマネジャーの養成にも力を入れている。また、プロダクトマネジメントに関する話題を中心とした「Stylish Ideaニューズレター」も毎週発行している。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア