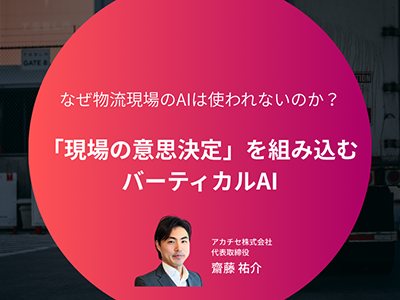“日本人はチームワークが得意”という常識の嘘―「高業績チーム」の知恵とイノベーションの関係
(第12回)イノベーションに効く洋書05:“The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization”
変革をうまく進め、業績を良くする“高業績チーム”の4つ効用
この本の発刊当時、日本では「チームの本」は数えるほどしかありませんでしたが、欧米ではすでにチームの本は数えられないくらいありました。
そのなかで、チームの本を作ることになったマッキンゼーのパートナーだったジョン・カッツェンバック氏とダクラス・スミス氏は、どのようにチームを作るかというハウツーものではなくて、変革や業績向上に取り組んできた人たちが実際の経験からチームについてどういった考え方を持っているかを調査し、まとめることにしました。そしてできたのがこの本です。
この調査を通じて、当時でも常識的な発見と、当時では意外な発見がありました。常識的な発見としては、
- 達成目標の高さがチーム形成につながる
- チームの基本原則を規律正しく実行することがたいていの場合見過ごされている
- 組織のどこにでもチームによる業績改善のポテンシャルが存在する
- 経営陣によるチームが最も難しい
- たいていの組織では、責任の所在をチームより個人に置きたがるという本質的傾向がある
といったものでした。
一方で意外な発見には、
- 高業績チームでは、チームリーダーはそれほど重要ではない
- どのメンバーも異なる局面でリーダーの役割を務める
- 誰がリーダーかわかりにくい
というものでした。
これはマッキンゼーの後輩である伊賀さんの指摘していることと同じことであり、おそらくマッキンゼーのチームのイメージであり、今では欧米の常識になっていることなのだと思います。
この本では調査から、変革をうまく進め、業績を良くするうえでのチームの効用を、以下の4つにまとめています。
- 構成メンバーの能力を超えるスキルや経験を集め、統合できる
- 明確な目標やアプローチを共に考え作っていくうちに、「同時進行での問題解決」や「先手をとる打ち手の実施」に有効なコミュニケーションを確立できる
- 仕事の持つ経済性、管理的側面での改善をもたらすユニークな方法を提供してくれる
- チームは楽しい
そして本書では、このようなチームの効用を活かすことのできる「真のチーム」になるための条件を示しています。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

好川 哲人(ヨシカワ テツト)
有限会社エムアンドティ取締役、株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表取締役、技術士、MBA
技術経営のコンサルタントとして、数々の新規事業開発や商品開発プロジェクトを支援、イノベーティブリーダーのトレーニングを手掛ける。「自分に適したマネジメントスタイルの確立」をコンセプトにしたサービスブランド「PMstyle」を立上げ、「本質を学ぶ」を売りにしたトレーニングの提供をしている。※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア