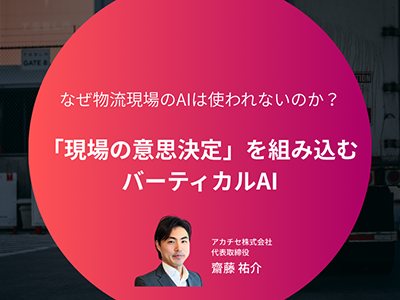前回(第17回)から、連載の総まとめとして、何を理解していただきたかったかを整理しています。ビジネスモデルの構築には、会計的な発想が必要で、かつ関係が深いのです。そこには、損益計算だけでなく、貸借対照表とキャッシュフローを加えた、総合的な見方が必要です。今回は、ビジネスモデルとビジネスモデル会計の関係を、ドラッカーが提唱する「5つの計器」から整理します。
ドラッカーが提唱する「5つの計器」から、ビジネスモデルの評価基準を学ぼう
マネジメントの父と呼ばれるP・F・ドラッカーは、「会社がどのように事業を運営し、正しい方向に向かっているのかをチェックする必要があり、そのためには、たくさんの計器をチェックする必要はなく、5種類もあればよい」と述べています。この5つの計器は、ビジネスモデルを検証するためにも欠くことのできない重要な計数です。目標に向かって進むためにチェックする「重要業績評価指標(KPI:Key Performance Indicator)」です。ドラッカーの指摘する5つの計器とビジネスモデルの関係について考えてみます。
5つの計器とは、
- 市場における地位
- イノベーションの成果
- 生産性
- 流動性とキャッシュフロー
- 収益性
のことです。
第1の「市場における地位」ですが、計数で考えると、シェア、売上高、生産高のことです。シェアや売上高が大きい企業は、価格交渉力がアップし、仕入単価の低下、すなわち変動費の低下につながります。さらに生産・販売数量の増加は、製品1個当たりの固定費(製造固定費、販売固定費)を低下させます。市場における地位を考えることは、どのように原価を低下させていくかを考えることにつながり、ビジネスモデルのコスト構造(C$)の課題になるのです。
ビジネスモデルキャンバスとの関係で説明すれば、顧客セグメント(CS:Customer Segments)をシッカリ決めないと、市場が明確になりません。そこで必要になるのは戦略ドメイン(顧客、ニーズ、独自能力)すなわち事業領域の設定です。ターゲットとなる市場の顧客へ提供する付加価値(VP:Value Propositions)を生みだす源泉として、どのようなヒト、モノへ投資(KR:Key Resources)するかが検討課題です。その結果、活動(KA:Key Activities)コストである固定費が発生し、原価集計法やコスト削減などの原価の問題へとつながります。
この記事は参考になりましたか?
- 新規事業計画に役立つ「経営分析・管理会計」の考え方・活かし方連載記事一覧
-
- ビジネスモデル会計がめざすもの-究極の計数感覚
- ドラッカーの教えから学ぶビジネスモデルの評価基準
- ビジネスモデルに必要な会計思考
- この記事の著者
-

千賀 秀信(センガ ヒデノブ)
公認会計士、税理士専門の情報処理サービス業・株式会社TKC(東証1部)で、財務会計、経営管理などのシステム開発、営業、広報、教育などを担当。18年間勤務後、1997年にマネジメント能力開発研究所を設立し、企業経営と計数を結びつけた独自のマネジメント能力開発プログラムを構築。「わかりやすさと具体性」という点で、多くの企業担当者や受講生からよい評価を受けている。研修、コンサルティング、執筆などで活躍中。日本能率協...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア