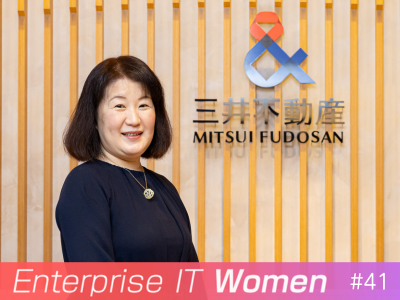日立は30万人規模のvSphere環境から「CaaS」を実現 自社で大規模導入した“経験知”を活用へ
ノウハウを生かした「DX」に最適なサービスを提供へ

企業がDXを進める中で、柔軟性や拡張性がないレガシーシステムが足かせとなっている。この問題を解決するためにパブリッククラウドなどに移行し、インフラをモダナイズ。さらにコンテナなどクラウドネイティブな技術を用いてアプリケーションもモダナイズすることで、DXで求められるアプリケーション開発のスピードの向上を実現する。このような“DXのための取り組み”の重要性は理解されつつあるが、実際にコンテナを活用しその恩恵を受けている企業はまだまだ少ない。IPAの「DX白書 2021」によれば、既にコンテナを全社的あるいは事業部で活用している、活用を検討している企業を合わせた割合は24.5%しかない。米国はこの割合が75.6%もあり、大きな差となっているのが現状だ。
日立が考える、企業においてDXが進まない理由
企業がDXで出遅れる原因に、まずはエンジニア不足が挙げられる。レガシーシステムのクラウド移行などの要望は増えているが、それができるエンジニアが足りないのだ。加えて、コンテナ技術の活用となると、さらにエンジニアは少ない。
たとえば、DXを進めるためにSoR(System of Record)とSoE(System of Engagement)を使い分けるような「バイモーダルIT」を実現することも必要だろう。その際にSoEでは、新たに自動化したCI/CDの実現などが求められる。「それらは従来のSoRにはなかったもので、技術者が新たに取り込まなければなりません」と指摘するのは、株式会社日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部 基盤開発本部 デジタル基盤サービス部 技師の山崎康博氏だ。

デジタル基盤サービス部 技師 山崎康博氏
また、クラウドネイティブやコンテナ技術を導入しても、いまひとつメリットがわからないことも課題だ。これらの技術を導入することは、DXにつながるアプリケーションのリリースサイクルを迅速化することが最大の目的だ。そのため、コストをかけてこれに取り組むのであれば、その効果をしっかりとマネージメント層などに伝える必要がある。効果がわからないまま進めると、余計な運用管理の手間やコストが増えるとの話になりかねない。
他にもDXが進まない課題として、クラウドネイティブやコンテナ技術を活用する運用組織や体制が整っていないケースもある。コンテナの恩恵は、主にアプリケーション開発者が受ける。そうなるとコンテナ環境の運用管理も、開発者が行うというケースもでてくるだろう。一方でアプリケーションの信頼性は、インフラ側の冗長化などで担保するのがこれまでの考え方だが、クラウドネイティブ化するとアプリケーション側でも信頼性の確保が必要だ。このように、インフラ側とアプリケーション側でどのように分担すべきかについては、企業ごとに異なる。

たとえばコンテナプラットフォームのKubernetesを扱える人がアプリケーション開発側にいるため、PoCなどの段階ではインフラ管理も含め開発側で面倒を見るケースがある。それが本番展開になると「運用管理をインフラ担当側が担うように変化することもあります」と説明するのは株式会社日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部 基盤開発本部 デジタル基盤サービス部 技師の加藤雄三氏。コンテナに対する成熟度に応じ、運用管理体制も変化すると指摘する。
この記事は参考になりましたか?
- 【特集】VMware Tanzu「モダンアプリケーションへ舵を切れ」連載記事一覧
- この記事の著者
-

谷川 耕一(タニカワ コウイチ)
EnterpriseZine/DB Online チーフキュレーターかつてAI、エキスパートシステムが流行っていたころに、開発エンジニアとしてIT業界に。その後UNIXの専門雑誌の編集者を経て、外資系ソフトウェアベンダーの製品マーケティング、広告、広報などの業務を経験。現在はフリーランスのITジャーナリスト...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア