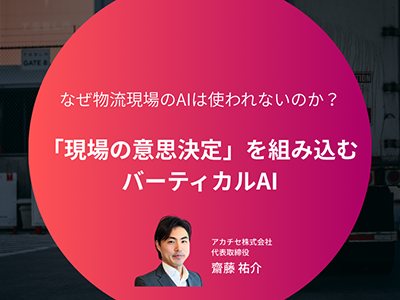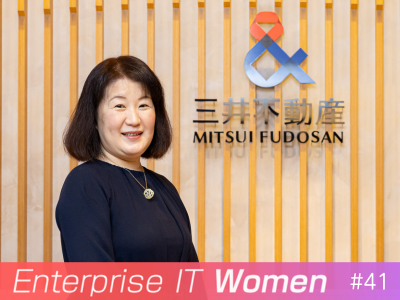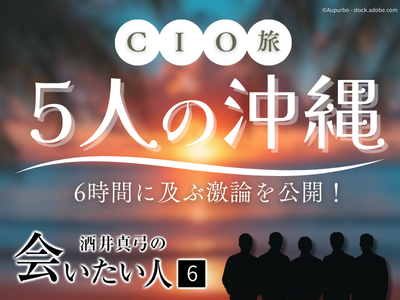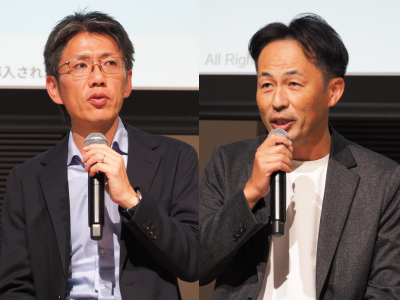「DX/デジタル変革」記事一覧
-
コープさっぽろ/日清食品GのIT費用管理術 AI台頭で状況が一変している今、CIOが担うべき役割とは
DXを推進してきた企業が、IT環境整備などの次に直面する課題として「IT費用管理」がある。クラウドやSaaSの利用が前提となり、AI活用も本格...
 2
2 -
なぜ物流現場のAIは使われないのか? 成果をわける「現場の意思決定」を組み込むバーティカルAI
近年、生成AIやAIエージェントの導入は急速に進んでいます。しかし、業界固有の知見が必要な現場では「PoC」止まりで本番運用に至らないケースも...
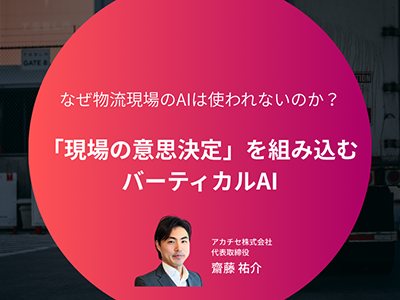 4
4 -
150人のIT人材をどう動かす?三井不動産が「AIエージェント」と「交換留学」で狙う組織の化学反応
三井不動産は、150人超が所属するDX本部を擁し、グループ会社を含めたDXを推進中だ。2025年4月には生成AIやデータ活用をリードする「DX...
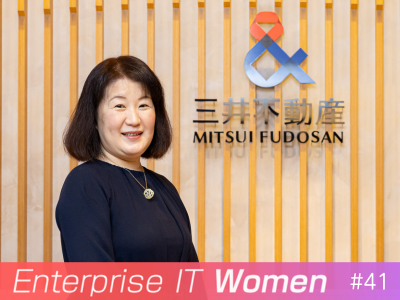 4
4 -
三井化学とIndeedが壊した「AI活用の壁」──“20年来のアドオン地獄”と“2年待ち”を打破
生成AIの登場により、企業のDXは「導入」から「実利の創出」という新たなフェーズへ突入した。しかし、AIを活用しようとしても、社内に散らばるデ...
 0
0 -
なぜシステムは使われないのか?効率化がDXを阻む逆説──サイロ化の罠とセカンドペンギンを増やす組織文化変革
「システムを導入したのに、誰も使わない」──この悩み、あなたの組織にもありませんか。実は、DXがうまくいかない原因の多くは技術ではなく、組織文...
 6
6 -
8,000人が働くトヨタ自動車の巨大工場で“失敗を許容”するには?──デジタル化を糸口に変革を探る
海外メーカーの台頭、EVシフト、SDV戦略など、日本の基幹産業である自動車業界は大きな転換期を迎えている。そんな中、トヨタ自動車の「ランドクル...
 13
13 -
2025年最も読まれた記事は? 富士通、Gemini、ソニー、デロイト……
読者の皆さまにとって2025年はどのような年になりましたか。今年は、AIエージェントをはじめとしたAIテクノロジーが市場を活性化するも、その活...
 5
5 -
【特集】ITベンダー&コンサル企業6社に聞く、2026年の展望 企業のIT変革を支えて見えた市場変化
「2025年の崖」の到来、AIエージェントの台頭、大企業に相次いだランサムウェア攻撃被害など、多様なトピックがIT業界を騒がせた2025年。D...
 3
3 -
【特集】CIO/CDO/CTOの6人に聞く、“岐路の一年”で得た手応えと展望──データ活用は次の段階へ
経済産業省が2018年の『DXレポート』で指摘した「2025年の崖」──問題提起から7年が経ち、岐路になる一年を終え、まもなく新年を迎えます。...
 20
20 -
【特集】財務・会計のキーパーソン5人に聞く──経済・テック・監査・実務のプロが2026年を見通す
「開示の質」が問われたサステナビリティ報告、「実務への実装」が試された生成AI、そして、「不確実性」を前提とした経営戦略の策定・実行……202...
 0
0 -
「広く浅いツール」を提供する情シスと「深い活用」を求める利用者……生成AIで実現する業務変革メソッド
生成AIへの注目が高まって数年が経過し、多くの企業が全社導入に踏み切った。しかし、導入したものの思うような成果が得られず、活用が進まないという...
 2
2 -
ナイキ、DHLでのIT要職を経て「ロッテ」のCIOに──丸茂眞弓さんが“集大成の場”で挑戦したいこと
ロッテは、IT基盤のモダナイズを経て、AI活用やカルチャー変革など新たなフェーズに突入した。リードするのは、2024年にCIOに就任した丸茂眞...
 8
8 -
“レジェンドCIO”5人衆と旅先で考える「これからの情シス」──2030年までに解決しておきたい課題
沖縄に5人のITリーダーが降り立った。激動のAI時代にあって走り続けることは大事だが、少し立ち止まって本音で語り合うことも、リーダーにとって必...
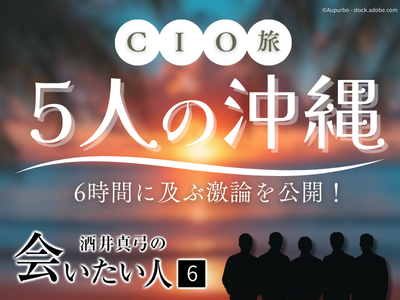 7
7 -
変革を遠ざける「DXじゃない論争」 ──「真のDX」論争が奪った5年と、AIが拓く新たな実装軸
「それはDXではない」という定義論争が、現場の変革を5年も停滞させた。小さな改善を否定する「真のDX」論から脱却し、AI時代の今こそ、現場の実...
 13
13 -
【中外製薬×ふくおかFG】AI時代のDX推進「実行・投資・文化醸成」の壁に、両社はどう立ち向かった?
DX推進において、アイデア創出から実行、スケール、そして組織変革まで、企業は必ず複数の「壁」に直面する。2025年10月21日に行われたエクサ...
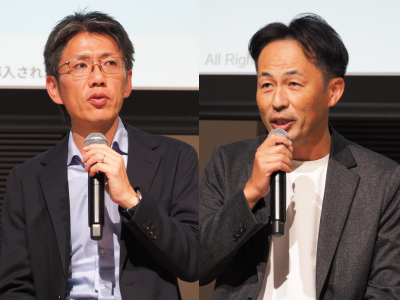 0
0 -
生成AI時代に“技術特化人材”は不要? 事業とITをつなぐ「CoE型人材」を育成する3のメソッド
多くの日本企業、特に規模の大きな日本の伝統的企業「JTC(Japanese Traditional Company)」では、デジタルや生成AI...
 3
3 -
松屋 古屋毅彦×テックタッチ 井無田仲──伝統と革新の両立を実現する、松屋銀座のデジタル変革の舞台裏
消費行動の多様化やECの台頭など、百貨店業界はかつてない変革期を迎えている。創業150年を超える老舗百貨店の松屋は、2025年5月1日に銀座店...
 0
0 -
生成AI活用が根付いたJTCのシステム部門は何をしたか?攻めの組織変革に有効な「バイブコーディング」
多くの日本企業、特に規模の大きな日本の伝統的企業「JTC(Japanese Traditional Company)」では、生成AIの活用に関...
 2
2 -
トライアルの西友買収でどんな“化学変化”が起こるのか?──技術革新を担うRetail AIに訊く
トライアルホールディングスは、7月1日付けで西友の全株式を取得し、完全子会社化を完了した。今後はセルフレジ機能付き「スキップカート」や顔認証決...
 17
17 -
安定経営の「真面目すぎる社風」を追い風に──老舗・キッツで“黒船CIO”が組織の沈黙に切り込む
創業75年を迎えるバルブ・流体制御機器メーカーのキッツ。2024年度に過去最高益を更新するなど、現在も成長を続けている。業績も安定している製造...
 1
1
1666件中1~20件を表示