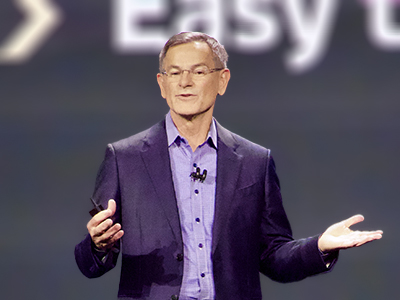「週刊DBオンライン 谷川耕一」一覧
-
2026年はAIエージェント「実行」の年へ UiPathが説く、7つのトレンドと日本企業の勝ち筋
2025年は、多くの企業にとって生成AIやAIエージェントの可能性を探る「パイロット(実証実験)」の年だった。対して2026年は、そのフェーズ...
 1
1 -
有事でSlackもTeamsも使えない、通信手段は? 米国防総省も頼る米Mattermostが進出へ
ランサムウェア被害が拡大する中、企業の事業継続計画(BCP)において見落とされがちなのが有事の通信手段だ。クラウド利用が当たり前の今、あえて「...
 3
3 -
AIで好調のOracleは「第4のハイパースケーラー」となれるか? 2026年の行方を占う
2025年、生成AIの進化はモデルの精度競争から、それをいかに実際のビジネスへ組み込むかという「エージェント活用」のフェーズへと移り変わった。...
 1
1 -
ガートナーに訊く、IT部門が招く「人材流出」 コロナ禍から6年、デジタルワークプレイスの変革が必要に
深刻化する人手不足は2030年代まで続くと予測される状況下、正社員の確保・定着は企業存続に関わる喫緊の課題だ。もはや、給与や福利厚生だけでは、...
 0
0 -
「Oracle AI Database 26ai」登場 次世代AIネイティブDBとオープン化戦略
米国時間10月14日、Oracle AI World 2025において「The “AI for Data” Revolution is Her...
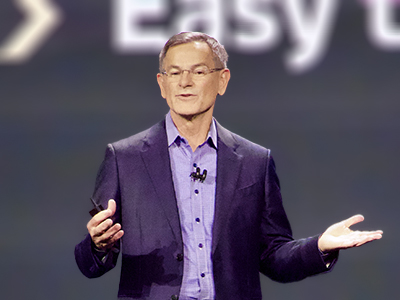 1
1 -
Oracleラリー・エリソン氏が描く「すべてが変わる」AIの時代 熱弁された次世代ヘルスケアの全貌は
2025年10月13日から米国ラスベガスで開催されたOracleの年次イベントは、名称を「Oracle CloudWorld」から「Oracl...
 0
0 -
国産SaaS連合が示したERPの「オフロード」という選択肢 SAPの“2027年問題”を解決できるか
多くの日本企業が「2025年の崖」や「SAPの2027年問題」という課題に直面し、レガシーとなった基幹システムの刷新を迫られている。複雑なアド...
 1
1 -
勝者はSalesforce、AI時代の主役は「データ」へ Informatica争奪戦で業界再編は?
生成AI、そして自律型エージェントAIの登場が、ビジネスを一変させようとしている。企業の競争優位性は、もはやアプリケーションの機能ではなく、そ...
 1
1 -
「脱VMware」の現実解とは? アイ・オー・データ機器に学ぶ、クラウド移行の戦略的アプローチ
BroadcomによるVMwareの買収、それにともなうライセンス体系の変更は、多くの企業にITインフラの根本的な見直しのきっかけを与えた。コ...
 1
1 -
AIはビジネスとITの「溝」を広げるのか? Gartnerが提言する、これからのアプリケーション戦略
企業のアプリケーション戦略とビジネス戦略には、乖離がある。2023年、Gartner(以下、ガートナー)がエンタープライズアプリケーションリー...
 0
0 -
ガートナーに訊く“AI時代”のデータ戦略、鍵は「データファブリック」と「アクティブメタデータ」
AIの急速な進化は、ビジネスのあらゆる側面において変革をもたらしている。「AI時代」における企業のデータ管理は、従来の手法のままでは通用しなく...
 3
3 -
IBMが仕掛ける半導体戦略、エコシステム拡充でAIニーズにどう応える 長年の研究開発を強みにできるか
IBMは、AI処理に特化した省電力チップ「AIU(Artificial Intelligence Unit)」、AI開発・実行環境「Vela」...
 0
0 -
2027年eKYC一本化、「犯収法改正」で変わる本人確認 厳格化を前に事業者はどう備える
2025年2月、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の改正を受けて「2027年4月より、インターネットバンキングなどの非対面取引における本人確認が...
 6
6 -
IBM zが「レガシー」ではない理由──z17に見る、AI時代のメインフレームの生存戦略
IBMが“AI時代”に向けて設計された最新メインフレーム「IBM z17」を発表した。独自のオンチップAIアクセラレーターを搭載し、ハードウェ...
 3
3 -
AIエージェントは部下か?ワークフローか?WorkdayとServiceNowのアプローチから考える
AIエージェントが急速に注目を集めており、多くのベンダーが“AIエージェント機能”の提供をはじめた。今後さまざまな業務がAIエージェントに置き...
 0
0
402件中1~15件を表示