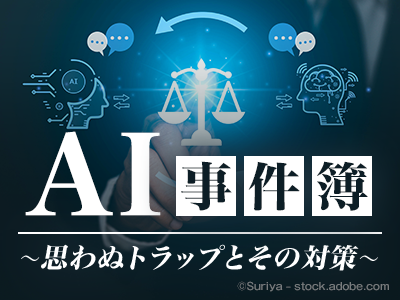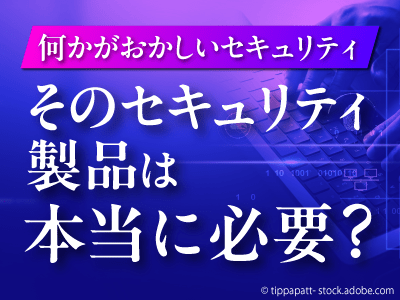「システム運用」記事一覧
-
三角育生教授が説く「戦略マネジメント層」の重要性──セキュリティリスクを経営陣に理解してもらうには?
現代ビジネスにおいて、DX推進は企業の持続的成長に不可欠な要素となっている。しかし、その推進が加速するにつれて、サイバーセキュリティリスクも増...
 1
1 -
教員がAIを欺いて学生の“ズル”を回避? 進化する「AI騙し」に対抗できる組織のセキュリティ強化術
生成AIやAIエージェントの活用気運が高まる中、そこに潜むリスクを認識し、組織として適切に対応するための体制を整えることは、AI活用に取り組む...
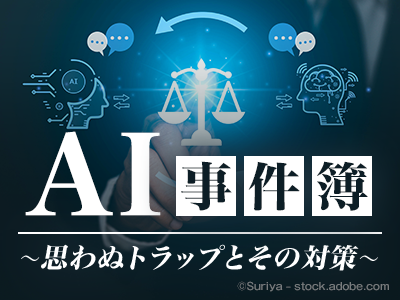 15
15 -
そのセキュリティ製品は自社にとって本当に必要か?真に対策すべきリスクを分析・把握する手順を押さえよう
情報セキュリティ対策製品やツールの需要は相変わらず高い。海外のみならず、日本国内の企業を狙ったサイバー攻撃やセキュリティ侵害の数は増える一方で...
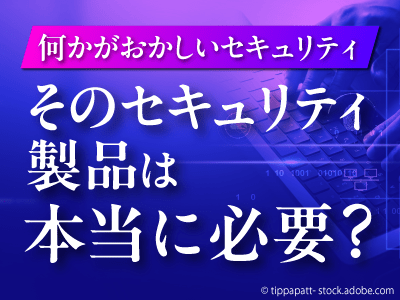 5
5 -
システム開発を発注したが、個別契約の一部が履行されなかった……それでも費用は「全額」支払うべき?
本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム開発を発注したが、個...
 0
0 -
国内最大級のSaaS企業ラクスはあえてオンプレミス強化 「クラウドネイティブ・オンプレミス」戦略とは
パブリッククラウドが当然視される時代、創業25年を迎えるSaaS企業のラクスは一貫してオンプレミスを堅持してきた。「楽楽精算」をはじめとするバ...
 0
0 -
ベンダーに発注した「アジャイル開発型プロジェクト」が頓挫、責任は誰にある? 管理義務の本質を考えよう
本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「ベンダーに発注した『アジャイ...
 3
3 -
日本企業が誤解している“単なるデジタル化”とDXの大きな違い 突破口となる「横をつなぐ人」に必要な力
多くの日本企業、特にいわゆるJTC(Japanese Traditional Company)では、DXが掛け声倒れに終わるケースが少なくあり...
 7
7 -
形だけのDXプロジェクト決裁者が起こす突然の「ちゃぶ台返し」をどう防ぐ?すぐに実践できる現実的対応策
連載「PM歴20年超の橋本将功が示す“情シスPMあるある”とその打ち手」では、プロジェクトマネージャー(PM)として20年以上キャリアを積んで...
 3
3 -
インド現地取材で見えた“オフショアの変化”──「静かな巨人」HCLTechからひも解く
AIやクラウドの浸透が企業ITを再定義しつつある今、システムやアプリケーションの設計・運用の在り方も変わってきた。長年オフショア先としても重用...
 1
1 -
パナソニックコネクトは再生を阻む伝統企業の壁をどう突破するのか?/榊原CTOが「Blue Yonder」と「SRE」による戦略を語る
業績の低迷や人員削減など苦境に立たされ、構造改革と事業選別の真っただ中にあるパナソニックグループ。その中でパナソニックコネクトは、B2B分野の...
 5
5 -
経営層の「流行りDX」に翻弄される担当者に捧ぐ!億単位の“尻切れトンボ”プロジェクトを防ぐ5つの要点
生成AIやAIエージェントなど、新たな技術が次々に登場する中、多くの企業ではこうした新技術を取り入れたプロジェクトが進行していることでしょう。...
 5
5 -
PagerDuty CEOが語る「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のAIエージェント活用──システム運用の効率化で課題解決に挑む
生成AIやAIエージェントがビジネスとテクノロジー領域を席巻する中、システム運用分野では人手作業の自動化が進み、業務に革命的変化をもたらしてい...
 0
0 -
「開発は一時、運用は一生」セイコーエプソンの運用集約に挑むITサポート部が開発段階から目を光らせる
社内に分散しているシステム運用を集約し、効率化と品質向上を目指すセイコーエプソンのITサポート部。2022年の新設以来、システム構築と運用業務...
 15
15 -
「答えられません」を正しく言えるAIの作り方:プログラミングの質問に答える政策AIボットは何が問題か
連載「AI事件簿 ~思わぬトラップとその対策~」では、過去のAIに関するインシデント事例や先人たちの教訓をもとに具体的なリスク対策を解説してい...
 2
2 -
マイナビがヘルプデスク対応を年間35%自動化した軌跡:アプリで実現する“問い合わせ民主化”の成果とは
マイナビでは、急速な事業拡大による社員数の増加、社用ITデバイスや働き方の多様化などにともない、社員のITデバイス・社内システム利用をサポート...
 9
9 -
DXとセキュリティの融合法とは──経営層が自組織に見合ったリスクマネジメントを実現する4つのポイント
サイバーセキュリティはDXの観点から見ても欠かせないものだが、DXと同レベルで重要視している組織はあまり多いとはいえない。いまだにセキュリティ...
 1
1 -
両利きの経営が求められる昨今、進化のカギを握るのは「運用のモダナイズ」──企業変革の起爆剤に
現代のビジネス環境は、かつてない速度で変化しており、この変化は企業のIT運用に大きな影響を与えています。特に、クラウドシフトやアプリケーション...
 5
5 -
「馴れ合い状態」のベンダーを一掃するには?攻めのIT戦略を叶える“良いベンダー”を見抜く3つの視点
DXをはじめとするITプロジェクトを進めるにあたっては、多くの企業が外部ベンダーと協力していることでしょう。しかし「付き合いのあるベンダーがあ...
 3
3 -
「“リアル”な自社特化型シナリオで備えよ」ランサムウェアの身代金要求に負けない“柔軟な”組織の作り方
KADOKAWAのランサムウェア被害をきっかけに、あらためて「サイバー攻撃者による身代金支払い要求に応じるべきか否か」という問題がクローズアッ...
 3
3 -
“マルチベンダーの無統治状態”が生むプロジェクト崩壊をどう防ぐ? 適切な統治者を置くためのポイント
連載「PM歴20年超の橋本将功が示す“情シスPMあるある”とその打ち手」では、プロジェクトマネージャー(PM)として20年以上キャリアを積んで...
 5
5 -
「担当者はイノベーションの一翼を担う自覚を」 ビジネス視点の投資が生む“必要十分”なセキュリティとは
経営を揺るがす情報セキュリティインシデントが後を絶たない中、企業の生存戦略としてのリスクマネジメントはどのようにあるべきだろうか。今、CIOや...
 0
0 -
社内派閥でプロジェクトが頓挫寸前……DXを妨害する「抵抗勢力」を味方につけるプロジェクト推進手法とは
ほぼすべての企業が行っているといっても過言ではないDXプロジェクト。こうしたプロジェクトを推進する上で、一番攻略が難しいのは「人」の要素です。...
 11
11 -
導入急がれる「AIOps」成功のポイント──コストと時間をドブに捨てないために
「AIOps」は、従来のシステム運用を大きく変革するだけのポテンシャルを有しているでしょう。事実、筆者の所属するPagerDutyのデータによ...
 0
0 -
「AIOps」で属人化したシステム障害管理は変わるのか、仕組みとユースケースからひも解く
ここ数年のうちに「AIOps」という単語を耳にすることが増えたのではないでしょうか。AIなどを用いることでITシステム運用を自動化、最適化する...
 0
0 -
日進月歩で進むAI技術の統制は「アジャイル」に──“民”と“官”のハブとなるAIガバナンス協会の挑戦
生成AIの急速な普及を受けて世界各国でAI規制に関する議論が加速する中、民間事業者においても政策決定に積極的にコミットする動きが活発化してきた...
 0
0
415件中1~20件を表示