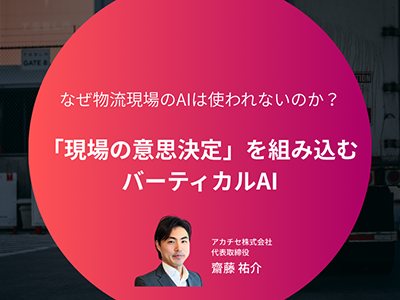「データ分析/活用」記事一覧
-
AI導入後に2年停滞も「ゼロ化」の視点により2ヵ月で改善──AIをポイントソリューションにしない術
大手企業でもAI活用が進む中、想定した成果を上げられていないケースは少なくありません。連載「AI活用の真髄──効果的なプロセスデザインとビジネ...
 2
2 -
ITリーダーは生成AIへの「憧れ症候群」に注意せよ──役割と選択肢が増える中で陥る意思決定の罠とは?
AI技術の進化により、企業の意思決定プロセスや組織の在り方が大きく変わろうとしている今、CIOをはじめとするITリーダーが果たすべき務めとは何...
 3
3 -
AIエージェント最前線──“文脈争奪戦”が始まった RAGの功罪、MCPの台頭……
2025年、「AIエージェント」が日本でも浸透してきた。市場には多くのベンダーが勃興する中、企業における担当者はどのように状況を俯瞰すればよい...
 13
13 -
ビジネスマンの“時間を奪う”メールこそ生成AI活用を!Gmailに出現した「Gemini」活用の一歩
第1回に引き続きJagu’e’r GWS 分科会のメンバーがお届けします。今回は、普段、営業職の奥原とエンジニア職の野間が、それぞれの専門知識...
 29
29 -
AIエージェントには「“新人教育”を施す必要がある」実際の活用事例から覗く、業務適用の現在地
昨今、高い注目が集まっている「AIエージェント」。AIエージェントはこれまでのAIの進歩の延長線上にあるが、どのような特徴があるのか皆さんはご...
 5
5 -
【SAP】JouleからAI Foundationまでの活用事例、Perplexityとの提携も
SAPは企業向けAIソリューション「SAP Business AI」を急拡充し、2025年5月時点で230以上の生成AIシナリオを実装、年末ま...
 1
1 -
データを「見えざる資産」に変えよ!AI時代の企業価値を高める「メタデータマネジメント」とは ── Quollio Technologies松元氏
企業のデータ活用現場で日々生じる、「意味のズレ」がDXの隠れたボトルネックとなっている。特に生成AIが企業の競争力を左右する時代において、その...
 28
28 -
デルが打ち出す“送電網”としてのAIインフラ マイケル・デルが示したエンタープライズAIの未来
人工知能(AI)は新たな「電力」であり、Dell Technologiesはその「送電網」となる──米Dell Technologies(以下...
 0
0 -
「20世紀のシステムはServiceNowに統合される」業績好調のサービスナウ、CEOが見通す戦略は
“AIエージェントの時代”に突入している中、ServiceNowがプラットフォーム戦略に自信を見せている。同社 CEOのビル・マクダーモット(...
 2
2 -
パナソニックコネクトは再生を阻む伝統企業の壁をどう突破するのか?/榊原CTOが「Blue Yonder」と「SRE」による戦略を語る
業績の低迷や人員削減など苦境に立たされ、構造改革と事業選別の真っただ中にあるパナソニックグループ。その中でパナソニックコネクトは、B2B分野の...
 5
5 -
【モダナイゼーション事例】人気記事を集めました! AI時代のインフラ刷新につながる特別イベントも開催
ITシステムを構築するということは、いつか廃棄し、新たなシステムへと移行することでもあります。新たなテクノロジートレンドが次々と生まれる中、ク...
 3
3 -
AI導入でかえって業務を増やしていないか? 成功企業と失敗企業の差は「プロセスデザイン」にあり
「AI」を導入したものの、想定していた効果を上げられていない……そのような企業に有益な方策の一つが、最適な業務プロセスを構築するための「ビジネ...
 8
8 -
アドビが発表したAIエージェントによる新たな収益モデル/ウォールストリートも歓迎する2つめの収入源とは?
アドビが「Adobe Summit 2025」で新たなAIエージェント戦略を発表した。その中核となる新基盤「Adobe Experience ...
 0
0 -
日本市場で息巻く「オブザーバビリティ」の活況はこの先も続くのか?──ガートナー米田氏に将来予測を訊く
「クラウドネイティブ」や「マイクロサービスアーキテクチャ」といったITインフラのモダナイゼーションを象徴するコンセプトとともに、それらのコンセ...
 1
1 -
経営層の「流行りDX」に翻弄される担当者に捧ぐ!億単位の“尻切れトンボ”プロジェクトを防ぐ5つの要点
生成AIやAIエージェントなど、新たな技術が次々に登場する中、多くの企業ではこうした新技術を取り入れたプロジェクトが進行していることでしょう。...
 5
5 -
PagerDuty CEOが語る「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のAIエージェント活用──システム運用の効率化で課題解決に挑む
生成AIやAIエージェントがビジネスとテクノロジー領域を席巻する中、システム運用分野では人手作業の自動化が進み、業務に革命的変化をもたらしてい...
 0
0 -
Google Cloudが急ピッチで進めるAIエージェント戦略、50社の賛同集めた「A2A」とは
Google Cloudは4月9日~11日、米ラスベガスで「Google Cloud Next 2025」を開催。AIエージェントの戦略を大き...
 2
2 -
【ユーザー会直伝!】Google Workspaceに統合が進む生成AI「Gemini」を有効活用するには
ビジネスの現場では、効率化と生産性向上が常に求められています。特に昨今は、リモートワークやハイブリッドワークの普及により、デジタルツールの重要...
 33
33 -
Amazon Q Developerで解決するメインフレーム移行の技術的課題──AIによるレガシーマイグレーションの成功要因とは?
長年企業を支えてきたメインフレームシステムは、維持コストの高さ、エンジニア人材の不足、ビジネス変化への対応の遅さという三重の課題に直面している...
 0
0 -
「今さらペーパーレス?」と侮るなかれ──“デジタルアレルギー”を克服した常陽銀行の驚くほどの徹底ぶり
「銀行取引の変容は20年前から兆候があった。ゆでガエルにならないためにできることを確実に」──そう語るのは、常陽銀行 経営企画部 副部長 兼 ...
 11
11
1064件中141~160件を表示